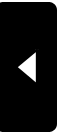2022年05月19日
検索 泉小太郎の開発地域 2<泉小太郎伝説の実際(90)>
山清路マップ
民話では泉小太郎が犀龍に乗り堤の縁を突き破ったされる山清路です。
犀川の要所で右岸と左岸の崖が接近しており、川の狭さという点では最も狭い場所と言っていいかと思います。
ウィキペディアも参照してみましょう。
山清路 ウィキペディアより
飛騨山脈(北アルプス)を水源とする犀川は、松本盆地を過ぎて長野盆地へと至る間、蛇行を繰り返しながら深い峡谷を成す。犀川は生坂村にて支流の金熊川(かなくまがわ)と麻績川(おみがわ)を合流させており、このあたり延長1キロメートルの区間が名勝・山清路とされている。
地名の由来は諸説あり、『角川日本地名大辞典』によれば、犀川・金熊川・麻績川という三川(三つの川)が交わる所からだとか、「山清寺」という名の寺にちなむともいう。また、『安曇の古代』の著者・仁科宗一郎は『仁科濫觴記』の記述から、古代に治水のための工事(=山征)が行われた場所、すなわち「山征地」から来たと推察している
うっすらとした過去の記憶では、このウィキペディアの記事が仁科濫觴記との最初の出会いだったと記憶しています。この記事を見て、仁科濫觴記を手に入れたことから新たな発見にあふれる旅につながりました。
ただあえて言うならこの記事は少し間違っていて、仁科宗一郎さんは「仁科濫觴記」にある「山征地」は、今ある山清路に比定されると述べているに過ぎません。
仁科宗一郎さん自体は、この山清路は「岸壁を壊すには古代の技術では厳しいほど硬いこと」「下流から岸壁を壊したなら当然発生する巨石等のガレキ等が見つからない」「そもそも、この上流域からは縄文時代からの生活遺跡が発見されているため、水位は今と縄文時代とそれほどかわらない」という論拠から、ここを切り開いて湖を水田にした説にはかなり懐疑的であります。
仁科宗一郎さんらしい納得感あふれる解説です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

民話では泉小太郎が犀龍に乗り堤の縁を突き破ったされる山清路です。
犀川の要所で右岸と左岸の崖が接近しており、川の狭さという点では最も狭い場所と言っていいかと思います。
ウィキペディアも参照してみましょう。
山清路 ウィキペディアより
飛騨山脈(北アルプス)を水源とする犀川は、松本盆地を過ぎて長野盆地へと至る間、蛇行を繰り返しながら深い峡谷を成す。犀川は生坂村にて支流の金熊川(かなくまがわ)と麻績川(おみがわ)を合流させており、このあたり延長1キロメートルの区間が名勝・山清路とされている。
地名の由来は諸説あり、『角川日本地名大辞典』によれば、犀川・金熊川・麻績川という三川(三つの川)が交わる所からだとか、「山清寺」という名の寺にちなむともいう。また、『安曇の古代』の著者・仁科宗一郎は『仁科濫觴記』の記述から、古代に治水のための工事(=山征)が行われた場所、すなわち「山征地」から来たと推察している
うっすらとした過去の記憶では、このウィキペディアの記事が仁科濫觴記との最初の出会いだったと記憶しています。この記事を見て、仁科濫觴記を手に入れたことから新たな発見にあふれる旅につながりました。
ただあえて言うならこの記事は少し間違っていて、仁科宗一郎さんは「仁科濫觴記」にある「山征地」は、今ある山清路に比定されると述べているに過ぎません。
仁科宗一郎さん自体は、この山清路は「岸壁を壊すには古代の技術では厳しいほど硬いこと」「下流から岸壁を壊したなら当然発生する巨石等のガレキ等が見つからない」「そもそも、この上流域からは縄文時代からの生活遺跡が発見されているため、水位は今と縄文時代とそれほどかわらない」という論拠から、ここを切り開いて湖を水田にした説にはかなり懐疑的であります。
仁科宗一郎さんらしい納得感あふれる解説です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年05月18日
検索 泉小太郎の開発地域 1<泉小太郎伝説の実際(89)>
「泉小太郎」こと「あまのひかる」は何処を開発したのか。実はこれが「泉小太郎伝説」をめぐる僕の探索のスタートでした。
「泉小太郎伝説」を知り、その物語が、僕が高校時代に感じた「この地域は湖だったのではないか」という思いとあまりにも内容が酷似していたため、興味を持ち調べ始めたのがきっかけだったと以前にも述べました。
また全く別の視点ですが農学部出身の私としては、この長野県の山間部に切り込んでいく水田や、川の水位のはるか高い場所まで開かれている水田に魅せられていました。
泉小太郎伝説を知る前に、この地の水田がどのように開発されていたのかを推測することがドライブ中の趣味ともなっていたのです。
その頃、特に特徴的だと思った場所が
① 仁科神明宮が鎮座する池田町付近の「農具川水系の高地にある不思議な水田」
② 田沢神明宮付近の「谷間に点在する不思議な水田」
でした。
この二つを知りながら「泉小太郎伝説」と出会い
①の「農具川水系の水田」は「仁科濫觴記」に描かれる「仁品王」が「九頭子」に命じた水田開発
②の「田沢神明宮付近の谷間に点在する水田」は「田沢神明宮縁起」に描かれる「安曇野開発の初め」として
二つとも「泉小太郎伝説」に深く関連する場所であったことがわかるのです。
これらが、泉小太郎こと「ひかるくん」の功績であったかどうかは不明なのですが、仁科濫觴記(にしならんしょうき)にある仁品王の開発計画の中で、河川大臣とされた「九龍子」や「諏訪眷属」あるいは「保高見熱躬」たちによって開発された場所であるのは間違い無いかと感じるのです。
農具川水系の開発は、「仁科神明宮」「川会神社」という形でその意思を今に伝達してきているとも言えますし、「田沢神明宮」はまさに、この地の開発の始めとして遺された意思と言っていいとも感じます。
この二つの開発はかなりの実感をともなって間違いないと「感じる」のですが、伝承の中で一つ納得いかない場所がひっかかっているのです。
それは、信府統記や数々の泉小太郎伝説に描かれる、泉小太郎と犀龍が切り開いたとする「山清路」です。
泉小太郎伝説の中で、一番のハイライトと言って良いでしょう。堤の壁を犀龍にまたがり突き破るシーンです。
その地が山清路とされ、江戸時代には景勝地として観光客が訪れました。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
「泉小太郎伝説」を知り、その物語が、僕が高校時代に感じた「この地域は湖だったのではないか」という思いとあまりにも内容が酷似していたため、興味を持ち調べ始めたのがきっかけだったと以前にも述べました。
また全く別の視点ですが農学部出身の私としては、この長野県の山間部に切り込んでいく水田や、川の水位のはるか高い場所まで開かれている水田に魅せられていました。
泉小太郎伝説を知る前に、この地の水田がどのように開発されていたのかを推測することがドライブ中の趣味ともなっていたのです。
その頃、特に特徴的だと思った場所が
① 仁科神明宮が鎮座する池田町付近の「農具川水系の高地にある不思議な水田」
② 田沢神明宮付近の「谷間に点在する不思議な水田」
でした。
この二つを知りながら「泉小太郎伝説」と出会い
①の「農具川水系の水田」は「仁科濫觴記」に描かれる「仁品王」が「九頭子」に命じた水田開発
②の「田沢神明宮付近の谷間に点在する水田」は「田沢神明宮縁起」に描かれる「安曇野開発の初め」として
二つとも「泉小太郎伝説」に深く関連する場所であったことがわかるのです。
これらが、泉小太郎こと「ひかるくん」の功績であったかどうかは不明なのですが、仁科濫觴記(にしならんしょうき)にある仁品王の開発計画の中で、河川大臣とされた「九龍子」や「諏訪眷属」あるいは「保高見熱躬」たちによって開発された場所であるのは間違い無いかと感じるのです。
農具川水系の開発は、「仁科神明宮」「川会神社」という形でその意思を今に伝達してきているとも言えますし、「田沢神明宮」はまさに、この地の開発の始めとして遺された意思と言っていいとも感じます。
この二つの開発はかなりの実感をともなって間違いないと「感じる」のですが、伝承の中で一つ納得いかない場所がひっかかっているのです。
それは、信府統記や数々の泉小太郎伝説に描かれる、泉小太郎と犀龍が切り開いたとする「山清路」です。
泉小太郎伝説の中で、一番のハイライトと言って良いでしょう。堤の壁を犀龍にまたがり突き破るシーンです。
その地が山清路とされ、江戸時代には景勝地として観光客が訪れました。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年05月16日
コラム2 泉小太郎と道祖神 三九郎<泉小太郎伝説の実際(88)>
道祖神とは ウィキペディアより
道祖神は、厄災の侵入防止や子孫繁栄等を祈願するために村の守り神として主に道の辻に祀られている民間信仰の石仏であると考えられており、自然石・五輪塔もしくは石碑・石像等の形状である。中国では紀元前から祀られていた道の神「道祖」と、日本古来の邪悪をさえぎる「みちの神」が融合したものといわれる

道祖神は安曇野各地に多数点在しており、田園風景とあいまって安曇野観光のアイコンとなっています。
なぜ、こんなに安曇野には道祖神があるのでしょうか。
田沢神明宮の縁起には「道祖神は猿田彦大神なり 犀の神とも申す」という一文があります。すくなくとも江戸時代には道祖神信仰と「犀の神」信仰が習合されていた一つの証拠となります。
道祖神は「塞(さい)の神」と呼ばれていました。
それがこの地にもともとあった「犀(さい)の神」である泉小太郎もしくは犀龍信仰と習合されてひとつの信仰と発展していったのではないかとおもうのです。
ひょっとすると戦国時代以降 武田軍に攻め滅ぼされたあと 田沢神明宮の「犀信仰」が形を変えて「道祖神」というかたちで「サイ信仰」が継承されたのではないかと推察します。
もともとこの地域にはなんらかの大きな信仰形態が存在しており、武田軍がこの地域を壊滅させたあとも民間信仰だけは形をかえたり名前をかえたりして伝承されたのではないかと推察するのです。
「道祖神」といえば「三九郎」があります。

正月飾りやダルマ、書初めなどを焼いて無病息災を願う伝統行事で 全国的にも似たような行事がありますが、「三九郎」と呼ぶのは、長野県の中信地方だけのようです。 県内の他の地域では「どんど焼き」などと呼ばれておりもともとは「道祖神の祭り」と言われています。
そうなると三九郎も「犀信仰」とかかわりがあるのかもしれません。
祭の季節はドントやきの正月の松飾りを焼く時期に集約されていますが、江戸時代以前の状況はわからないのがこの三九郎でもあります。
ここで僕は田沢神明宮縁起の中に描かれる、犀川のほとりにかがり火を灯す祭りを思い浮かべました。
もともと三九郎とは川の補修のために、雑木を取り除き燃やした川の整備のための祭りがもともとあり、それが他の地域で行われていた正月飾りを燃やす「どんど焼き」などと習合されて「三九郎」という形でこの地域に広まったしれないと邪推するのです。
今でも消防の関係から、川原で三九郎をすることがありますが、あれの発生も泉小太郎の命じた「年に一度犀川のほとりにたいまつを灯す」という川を整備する祭りから発生したかもしれないと思い浮かべながら見ると、犀川の祭りの面影を思い浮かべ楽しむこともできます。
謎とされている三九郎の名前も
「犀川労 さいかわろう」みたいなところから変名したかもしれません。(笑)
道祖神も 三九郎も実は江戸以前の歴史がわからないのが実情で(なぜなら武田軍に壊滅させられていますから)起源も発祥も不明です。この2つはこの地域を特徴づける他の地域とは異なる祭りであり、おそらくは 江戸以前(戦国以前)の古代の信仰が、形や伝承を変え今に残されたものでないかと思うのです。
また道祖神を夫婦像としているのが安曇野の道祖神の特徴ですが、ひょっとするとあれは白竜王(九頭子)と犀龍(泉小太郎の母)の姿ではないかとも想像を膨らすこともできます。
仁科濫觴記には あまのひかる(泉小太郎)の母親が仁品王のもとにつかえ
開発地(九頭子とひかるがいる場所)に何度も通うシーンがあり
九頭子と小太郎の母親(未亡人?)の恋物語を連想させてもくれます。
そう思うと道祖神の2人は九頭竜と犀龍の二人に見えてくるから不思議なものです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
道祖神は、厄災の侵入防止や子孫繁栄等を祈願するために村の守り神として主に道の辻に祀られている民間信仰の石仏であると考えられており、自然石・五輪塔もしくは石碑・石像等の形状である。中国では紀元前から祀られていた道の神「道祖」と、日本古来の邪悪をさえぎる「みちの神」が融合したものといわれる

道祖神は安曇野各地に多数点在しており、田園風景とあいまって安曇野観光のアイコンとなっています。
なぜ、こんなに安曇野には道祖神があるのでしょうか。
田沢神明宮の縁起には「道祖神は猿田彦大神なり 犀の神とも申す」という一文があります。すくなくとも江戸時代には道祖神信仰と「犀の神」信仰が習合されていた一つの証拠となります。
道祖神は「塞(さい)の神」と呼ばれていました。
それがこの地にもともとあった「犀(さい)の神」である泉小太郎もしくは犀龍信仰と習合されてひとつの信仰と発展していったのではないかとおもうのです。
ひょっとすると戦国時代以降 武田軍に攻め滅ぼされたあと 田沢神明宮の「犀信仰」が形を変えて「道祖神」というかたちで「サイ信仰」が継承されたのではないかと推察します。
もともとこの地域にはなんらかの大きな信仰形態が存在しており、武田軍がこの地域を壊滅させたあとも民間信仰だけは形をかえたり名前をかえたりして伝承されたのではないかと推察するのです。
「道祖神」といえば「三九郎」があります。

正月飾りやダルマ、書初めなどを焼いて無病息災を願う伝統行事で 全国的にも似たような行事がありますが、「三九郎」と呼ぶのは、長野県の中信地方だけのようです。 県内の他の地域では「どんど焼き」などと呼ばれておりもともとは「道祖神の祭り」と言われています。
そうなると三九郎も「犀信仰」とかかわりがあるのかもしれません。
祭の季節はドントやきの正月の松飾りを焼く時期に集約されていますが、江戸時代以前の状況はわからないのがこの三九郎でもあります。
ここで僕は田沢神明宮縁起の中に描かれる、犀川のほとりにかがり火を灯す祭りを思い浮かべました。
もともと三九郎とは川の補修のために、雑木を取り除き燃やした川の整備のための祭りがもともとあり、それが他の地域で行われていた正月飾りを燃やす「どんど焼き」などと習合されて「三九郎」という形でこの地域に広まったしれないと邪推するのです。
今でも消防の関係から、川原で三九郎をすることがありますが、あれの発生も泉小太郎の命じた「年に一度犀川のほとりにたいまつを灯す」という川を整備する祭りから発生したかもしれないと思い浮かべながら見ると、犀川の祭りの面影を思い浮かべ楽しむこともできます。
謎とされている三九郎の名前も
「犀川労 さいかわろう」みたいなところから変名したかもしれません。(笑)
道祖神も 三九郎も実は江戸以前の歴史がわからないのが実情で(なぜなら武田軍に壊滅させられていますから)起源も発祥も不明です。この2つはこの地域を特徴づける他の地域とは異なる祭りであり、おそらくは 江戸以前(戦国以前)の古代の信仰が、形や伝承を変え今に残されたものでないかと思うのです。
また道祖神を夫婦像としているのが安曇野の道祖神の特徴ですが、ひょっとするとあれは白竜王(九頭子)と犀龍(泉小太郎の母)の姿ではないかとも想像を膨らすこともできます。
仁科濫觴記には あまのひかる(泉小太郎)の母親が仁品王のもとにつかえ
開発地(九頭子とひかるがいる場所)に何度も通うシーンがあり
九頭子と小太郎の母親(未亡人?)の恋物語を連想させてもくれます。
そう思うと道祖神の2人は九頭竜と犀龍の二人に見えてくるから不思議なものです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年05月15日
検索 銅戈(どうか)7<泉小太郎伝説の実際(87)>
海ノ口の銅戈の発見当初の状況をより詳しく調べるために、大町市の図書館に向かいました。
この地方の様々な図書館を巡ってきましたが大町市の歴史に関する蔵書は素晴らしく、
2階の閲覧室にこもって1ヶ月でも読みあさっていたいと思えるほどの本が並んでいました。この地区の歴史研究が盛んに行われている証拠です。
市立大町図書館

ただ調べていた海ノ口神社の銅戈の発見に関しては、疑問符のつく内容がたくさんありました。
すこし説明します。
昭和初期、大町の学校の校長であった一志茂樹氏(いっし しげき、 1893年11月12日 - 1985年2月27日)はある時、海ノ口上神社の神宝の中に「銅戈」を発見します。
この発見は当時、銅戈発見最北の地として、弥生時代の文化を知る上での大きな材料となるものでした。
しかし発掘されたものではなかったためどこからの出土かわからず、その当時のはやりの説としてその出土地は姫川流域であるとされました。この主張は主に大場磐雄氏(おおば いわお、1899年9月3日 - 1975年6月7日)によってなされました。
この姫川からの進入説は大場氏が主張する、武南方(諏訪神)の日本海側からの流入や、安曇族の日本海側からの流入といった今でもある「流行」によるものですが、元を辿れば戦前の皇国史観により、より古い部族のほうが高貴であるという歪んだ歴史観により、日本海側の部族の流入のほうが歴史は古く、その時代からこの地は栄えていたとすることを地方がのぞんだ背景があります。
一志茂樹氏は、海ノ口神社の社家が幕末時に糸魚川根知の宮の神主をしていたことがあることから日本海側から持ち込まれたという説を唱えており傍証として「銅戈は発見時に根知の神社の古文書に包んであった」(大町史)ことをあげていますが、伝承中に管理者が神宝保存のために包む行為は普通にあり得ますので、発見場所を糸魚川周辺とするのにはかなり無理があると思います。
現在では弥生時代の遺跡が姫川沿いからまったく出土しないことなどから、南からの流入や千曲川方面からの流入説のほうが一般的になっています。
この後、大町市博物館にも行きました。
大町市博物館 資料館文化財センター

所蔵品として海ノ口神社の銅戈がある場所です。
大変、親切に対応してくれましたが「銅戈をみることができませんか」と尋ねたところ、すぐには見せられないところにしまってあるということ(事前の申し込み等が必要)で見ることが出来ませんでした。
また「銅戈を包んでいた古文書があったはずですが」と尋ねたところ
「そういうものは数十年前の時点で既に見当たらなかった」ということで
史料保存ができていないためか、もともとそんな古文書がなかったのか、どちらにしろ銅戈が海ノ口神社に伝わった経緯はわからないままでした。
包まれていたという古文書が残存すれば、もっと具体的な内容がわかったかと思いますが、現在は確認できません。
発見当初は磨かれたように黒光りしていて腐食もほとんどなかったということですが、今(?)の画像をみると緑のサビに覆われた状態になってしまっています。
ちなみに現在?海ノ口神社の銅戈の画像はこんな感じです。

保存状態が悪かったのではなかろうかと思います。発見当時、大場磐雄(おおばいわお)氏は拓本を取るなど、今としては問題のある行為を当時おこなってしまっていたりもしています。近年の研究でめずらしい鹿の紋などもみつかっているらしいですが、博物館に誰の目にも触れられず置かれている状態は非常に残念で少なくとも展示するか一刻も早く海ノ口神社に戻し神宝として信仰の対象として戻してあげたいと僕は思うのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
この地方の様々な図書館を巡ってきましたが大町市の歴史に関する蔵書は素晴らしく、
2階の閲覧室にこもって1ヶ月でも読みあさっていたいと思えるほどの本が並んでいました。この地区の歴史研究が盛んに行われている証拠です。
市立大町図書館

ただ調べていた海ノ口神社の銅戈の発見に関しては、疑問符のつく内容がたくさんありました。
すこし説明します。
昭和初期、大町の学校の校長であった一志茂樹氏(いっし しげき、 1893年11月12日 - 1985年2月27日)はある時、海ノ口上神社の神宝の中に「銅戈」を発見します。
この発見は当時、銅戈発見最北の地として、弥生時代の文化を知る上での大きな材料となるものでした。
しかし発掘されたものではなかったためどこからの出土かわからず、その当時のはやりの説としてその出土地は姫川流域であるとされました。この主張は主に大場磐雄氏(おおば いわお、1899年9月3日 - 1975年6月7日)によってなされました。
この姫川からの進入説は大場氏が主張する、武南方(諏訪神)の日本海側からの流入や、安曇族の日本海側からの流入といった今でもある「流行」によるものですが、元を辿れば戦前の皇国史観により、より古い部族のほうが高貴であるという歪んだ歴史観により、日本海側の部族の流入のほうが歴史は古く、その時代からこの地は栄えていたとすることを地方がのぞんだ背景があります。
一志茂樹氏は、海ノ口神社の社家が幕末時に糸魚川根知の宮の神主をしていたことがあることから日本海側から持ち込まれたという説を唱えており傍証として「銅戈は発見時に根知の神社の古文書に包んであった」(大町史)ことをあげていますが、伝承中に管理者が神宝保存のために包む行為は普通にあり得ますので、発見場所を糸魚川周辺とするのにはかなり無理があると思います。
現在では弥生時代の遺跡が姫川沿いからまったく出土しないことなどから、南からの流入や千曲川方面からの流入説のほうが一般的になっています。
この後、大町市博物館にも行きました。
大町市博物館 資料館文化財センター

所蔵品として海ノ口神社の銅戈がある場所です。
大変、親切に対応してくれましたが「銅戈をみることができませんか」と尋ねたところ、すぐには見せられないところにしまってあるということ(事前の申し込み等が必要)で見ることが出来ませんでした。
また「銅戈を包んでいた古文書があったはずですが」と尋ねたところ
「そういうものは数十年前の時点で既に見当たらなかった」ということで
史料保存ができていないためか、もともとそんな古文書がなかったのか、どちらにしろ銅戈が海ノ口神社に伝わった経緯はわからないままでした。
包まれていたという古文書が残存すれば、もっと具体的な内容がわかったかと思いますが、現在は確認できません。
発見当初は磨かれたように黒光りしていて腐食もほとんどなかったということですが、今(?)の画像をみると緑のサビに覆われた状態になってしまっています。
ちなみに現在?海ノ口神社の銅戈の画像はこんな感じです。

保存状態が悪かったのではなかろうかと思います。発見当時、大場磐雄(おおばいわお)氏は拓本を取るなど、今としては問題のある行為を当時おこなってしまっていたりもしています。近年の研究でめずらしい鹿の紋などもみつかっているらしいですが、博物館に誰の目にも触れられず置かれている状態は非常に残念で少なくとも展示するか一刻も早く海ノ口神社に戻し神宝として信仰の対象として戻してあげたいと僕は思うのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年05月14日
検索 銅戈(どうか)6<泉小太郎伝説の実際(86)>
弥生時代から古墳時代の転換期は、銅戈(銅矛を)主軸とした青銅器をつかった出雲国的風習(弥生時代の風習)が銅鏡、鉄剣、前方後円墳を主体とした皇族風習(古墳時代の風習)に入れ替わった時代ではなかったかと思うのです。
ただし、これについては今回の探索とは別の話ですので、省略します。またいつか述べるかもしれません。
とにかく田沢神明宮の銅戈は武田軍の進軍をさけ、初めは「仏崎」「坂木」と「穴」という隠し場所のある地域を経由して最終的にははるか北部に位置する「海ノ口」まで運ばれて神宝として守られたのかもしれません。
海ノ口の銅戈は発見当時は「磨かれたように綺麗だった」といいます。
大町史によれば
「色は全体に青黒く、わずかに光沢がある。全体に腐食もほとんどなく、欠損部分も見られず、保存状態はきわめて良好である。土中することなくそのまま伝世されたことは考えられないにしても、早い時期に出土し伝世したことがうかがわれる。」とある
この銅戈をめぐる説では、どこかで発掘後、磨かれて海ノ口に運ばれて神宝にされたというものが多いのですが、僕は「埋められなかった銅戈」ではないかと思うのです。
実際に、田沢神明宮では「犀の広鉾」として武田軍の侵攻までの16世紀までは銅戈が埋められず祀られていたという縁起もあることから埋められることなく、祭祀の対象とされていた青銅器はあり得るのです。
この海ノ口諏訪神社の銅戈が、田沢神明宮から逃げのびた「犀の角」なのか、あるいは弥生時代の祭祀の形跡をずっと白馬のふもとの木崎湖のほとりで伝承されてきた特異的な例なのか、どちらなのかはわからないものの、「弥生時代」に直接触れることのできる(いちども埋没されていない歴史)「神宝」であると私は思うのです。
本当の出土地がわからないため、考古学会としては中途半端な扱いになっていますが、ひょっとしたら「埋められたことのない弥生の儀式を伝承したもの」としての価値のほうがはるかに大きいかもしれません。そのフィクション(説)の上に立って捉え直し、銅戈が多量に発見された中野の柳沢遺跡の銅戈とコラボすることによって十分に観光資源になるのではと思っています。
現時点ではこの海ノ口の銅戈は
①どこかで出土した銅戈を祀ったものが神宝として伝承した
②もともと祭器として使った銅戈が埋められることなくこの海ノ口神社に神宝として伝承した
③田沢神明宮に祀られていた「犀の広鉾」が武田軍の進軍を避け遷移するなかで海ノ口までたどり着いた
などの可能性があり得ます。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年05月13日
城山公園の北(放光寺跡)に前方後方墳 発見されるかも?
今日5月13日の信濃毎日新聞 朝刊に
「松本に新たな前方後方墳か」という見出しで
県考古学会員 関沢聡さんが発表とありました。
この「泉小太郎を調べまくる」のブログを読んでいただいている方には
伝わるかもしれませんが
この記事を見たときに僕はかなり震えました。
この場所はまさに泉小太郎が育ったとされる「放光寺」の
敷地にあたる場所なのです。
参照 検索 放光寺


前方後方墳はこの地からすぐ近くにある弘法山が長野県最古であるとされ
その地も泉小太郎との関連性がある地として麓には泉小太郎の像もあります。

さらにまだ本ブログでは述べていませんが
泉小太郎が開拓の始めとして本名の「ひかる」の名を冠した
光城山の山頂も僕はおそらく前方後方墳もしくは前方後円墳の残りでは
ないかとおもっています。(もうじきその話題に触れます)


いかがでしょうか。
しかも弘法山古墳 そして放光寺跡の今回の城山 光城山はおなじ構造線の段丘上につづく沿線で
安曇野平を開拓したとされる泉小太郎伝説にはぴったりな位置関係です。
今日の発見はまさにこれらの証明をしてくれる大発見かもしれません。
さてGWをはさみ しばらく休止していた泉小太郎をしらべまくるをそろそろ
再開させていただきます。
いよいよ最終的な盛り上がりに向かって進んでいきます。
今日のべた光城山の山頂の遺跡(と僕は考えています)の発見も
含め 泉小太郎が何をしたかを探っていきたいと思います。
「松本に新たな前方後方墳か」という見出しで
県考古学会員 関沢聡さんが発表とありました。
この「泉小太郎を調べまくる」のブログを読んでいただいている方には
伝わるかもしれませんが
この記事を見たときに僕はかなり震えました。
この場所はまさに泉小太郎が育ったとされる「放光寺」の
敷地にあたる場所なのです。
参照 検索 放光寺


前方後方墳はこの地からすぐ近くにある弘法山が長野県最古であるとされ
その地も泉小太郎との関連性がある地として麓には泉小太郎の像もあります。

さらにまだ本ブログでは述べていませんが
泉小太郎が開拓の始めとして本名の「ひかる」の名を冠した
光城山の山頂も僕はおそらく前方後方墳もしくは前方後円墳の残りでは
ないかとおもっています。(もうじきその話題に触れます)


いかがでしょうか。
しかも弘法山古墳 そして放光寺跡の今回の城山 光城山はおなじ構造線の段丘上につづく沿線で
安曇野平を開拓したとされる泉小太郎伝説にはぴったりな位置関係です。
今日の発見はまさにこれらの証明をしてくれる大発見かもしれません。
さてGWをはさみ しばらく休止していた泉小太郎をしらべまくるをそろそろ
再開させていただきます。
いよいよ最終的な盛り上がりに向かって進んでいきます。
今日のべた光城山の山頂の遺跡(と僕は考えています)の発見も
含め 泉小太郎が何をしたかを探っていきたいと思います。