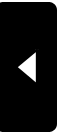2022年02月18日
検索 穂高神社1 <泉小太郎伝説の実際(10)>
ここからが本番です。ここからは今の時点でどこにも載っていない僕だけが知る情報です。(僕が知らないだけで誰かがすでに調べている可能性もありますが、そのような文書を発見できませんでした。)
さて、もし仁科宗一郎さんが推察したように、ひかるくんが仁品王と保高見熱躬(ほたかみのあつみ)との軋轢のなかで、保高見あつみ側についたとしたら、主に大町の記録である「仁科濫觴記(にしならんしょうき)」にその名を留めていなくても、穂高方面には、その伝承等が残っているのではないかと思いました。
そこで穂高神社に向かいました。

穂高神社 マップ
『穂高神社』(穂高神社ホームページより)
『穗髙見命を御祭神に仰ぐ穗髙神社は、信州の中心ともいうべき 安曇野市穂高にあります。そしてその奥宮は、北アルプス穂高岳のふもとの上高地に祀られており、嶺宮は、北アルプスの主峰奥穂高岳の頂上に祀られています。』
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
さて、もし仁科宗一郎さんが推察したように、ひかるくんが仁品王と保高見熱躬(ほたかみのあつみ)との軋轢のなかで、保高見あつみ側についたとしたら、主に大町の記録である「仁科濫觴記(にしならんしょうき)」にその名を留めていなくても、穂高方面には、その伝承等が残っているのではないかと思いました。
そこで穂高神社に向かいました。

穂高神社 マップ
『穂高神社』(穂高神社ホームページより)
『穗髙見命を御祭神に仰ぐ穗髙神社は、信州の中心ともいうべき 安曇野市穂高にあります。そしてその奥宮は、北アルプス穂高岳のふもとの上高地に祀られており、嶺宮は、北アルプスの主峰奥穂高岳の頂上に祀られています。』
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月18日
スタートライン! いよいよ泉小太郎伝説の探索が始まります。<泉小太郎伝説の実際(9)>
ここまでで「あまのひかるくん」に関する「仁科濫觴記(にしならんしょうき)」の記述は終わりました。
ここまでは、ネットを探って「仁科濫觴記」にたどりつき、「安曇の古代」という名著を手にすれば、何とか得られる情報です。
ただ先ほども説明したように
「仁科濫觴記」および「安曇の古代」「仁科宗一郎氏」のどれもが埋もれてしまっているため、
ここまでの情報ですら、知られていません。
そのどれかに一度でも触れればその正当性を理解できますし、少なくとも安曇研究家は必読であるべきです。
ここまでは今回の僕の探求の前段階です。
読みにくい文章で申し訳ありませんでした。
ここまできて「仁科濫觴記」にたどりつくまで約8年かかっています。
その8年間の探究は またいつかブログに載せようと思いますが
主に、ネット検索と、農業用水や水の流れに興味をもって
探求していました。
その時に、「安曇の古代」という「仁科濫觴記」の解説本を
手にした日から、怒涛の発見ラッシュとなるのです。
まるで、いままでかき集めてきたパズルの正解を手にしたように。
ここからの発見ラッシュをみると
「仁科濫觴記」が 偽書などではなく
時代時代ごとに手を加えられながら守られてきた
真実に近い伝承だったのではないかと思えてしかたがないのです。
さて
ここまでで8年間。
実際はそのほかの試行錯誤も同時に多数行っていますが今回は泣く泣く省略です
では、「泉小太郎」と後世で呼ばれるようになった「ひかるくん」(白水郎 日光)は
その後どうなったのか
本当にもう歴史の幕は下りたのか。いよいよここから、僕の探求が始まります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
ここまでは、ネットを探って「仁科濫觴記」にたどりつき、「安曇の古代」という名著を手にすれば、何とか得られる情報です。
ただ先ほども説明したように
「仁科濫觴記」および「安曇の古代」「仁科宗一郎氏」のどれもが埋もれてしまっているため、
ここまでの情報ですら、知られていません。
そのどれかに一度でも触れればその正当性を理解できますし、少なくとも安曇研究家は必読であるべきです。
ここまでは今回の僕の探求の前段階です。
読みにくい文章で申し訳ありませんでした。
ここまできて「仁科濫觴記」にたどりつくまで約8年かかっています。
その8年間の探究は またいつかブログに載せようと思いますが
主に、ネット検索と、農業用水や水の流れに興味をもって
探求していました。
その時に、「安曇の古代」という「仁科濫觴記」の解説本を
手にした日から、怒涛の発見ラッシュとなるのです。
まるで、いままでかき集めてきたパズルの正解を手にしたように。
ここからの発見ラッシュをみると
「仁科濫觴記」が 偽書などではなく
時代時代ごとに手を加えられながら守られてきた
真実に近い伝承だったのではないかと思えてしかたがないのです。
さて
ここまでで8年間。
実際はそのほかの試行錯誤も同時に多数行っていますが今回は泣く泣く省略です
では、「泉小太郎」と後世で呼ばれるようになった「ひかるくん」(白水郎 日光)は
その後どうなったのか
本当にもう歴史の幕は下りたのか。いよいよここから、僕の探求が始まります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月17日
検索 仁科濫觴記4 <泉小太郎伝説の実際(8)>
さて治水を終えた「ひかるくん」はどうなったでしょうか。
仁科濫觴記はその後の「ひかるくん」にも触れています。
⑧「ひかるくん」の妹 妹耶姫(いもやひめ)が仁品王との間に
「仁品王」政庁のその後
① 政庁を拡大しようとした「仁品王」に、
② それに腹を立てた「仁品王」が「保高見熱身躬」を叱責。
③「保高見熱躬」は怒って、都に帰り、「天皇」(まだ天皇という表現は
④「天皇」もそれを聞いて怒り、仁品の館を取り潰せというお達しをくだします。
⑤「仁品王」家はおとりつぶしになります。
⑥さらに「仁品王」は失念の中で死去、あとを追うように、長男の若王子、
⑦次男が仁品王政庁を担うものの、スケールダウンします。
仁科濫觴記はその後の「ひかるくん」にも触れています。
⑧「ひかるくん」の妹 妹耶姫(いもやひめ)が仁品王との間に
若君二人をもうけます。
⑨「ひかるくん」の母親(つまり犀龍)はその妹の世話役として
⑨「ひかるくん」の母親(つまり犀龍)はその妹の世話役として
宮廷(ではないけれど)に入ります。
⑩「ひかるくん」は仁品政庁の近くに「光明亭」(現在の大町市光明寺のあたり)
⑩「ひかるくん」は仁品政庁の近くに「光明亭」(現在の大町市光明寺のあたり)
という建物を与えられ、政権の一角を担います。

華々しいハッピーエンドです。
しかし、僕はここで少しの違和感をかんじました。
なぜなら、たつのこたろう伝説はどちらかというと悲壮感漂うエンディングで、大抵、龍の背にのって、たつのこたろうは消えていくのです。
もし仁科濫觴記にあるようなハッピーエンドであるのなら、民話ももっとハッピーエンドで終わるはずなのにと思ったのですが、仁科濫觴記を読み進めると、さらなる続きがあることがわかりました。ただし、「ひかるくん」の記載は一切なくあくまで「仁品王」の政庁のその後です。

華々しいハッピーエンドです。
しかし、僕はここで少しの違和感をかんじました。
なぜなら、たつのこたろう伝説はどちらかというと悲壮感漂うエンディングで、大抵、龍の背にのって、たつのこたろうは消えていくのです。
もし仁科濫觴記にあるようなハッピーエンドであるのなら、民話ももっとハッピーエンドで終わるはずなのにと思ったのですが、仁科濫觴記を読み進めると、さらなる続きがあることがわかりました。ただし、「ひかるくん」の記載は一切なくあくまで「仁品王」の政庁のその後です。
「仁品王」政庁のその後
① 政庁を拡大しようとした「仁品王」に、
最重臣、「保高見熱躬(ほたかみのあつみ おそらく穂高神社のはじめ。
おそらく安曇族の高位者)」が、民への負担増大を危惧して反対します。
② それに腹を立てた「仁品王」が「保高見熱身躬」を叱責。
(保高見を竹鞭で打つという記述もあります)
③「保高見熱躬」は怒って、都に帰り、「天皇」(まだ天皇という表現は
ないのですがわかりやすく表記)に対して報告。
④「天皇」もそれを聞いて怒り、仁品の館を取り潰せというお達しをくだします。
⑤「仁品王」家はおとりつぶしになります。
⑥さらに「仁品王」は失念の中で死去、あとを追うように、長男の若王子、
妹耶姫と次々に亡くなります。
⑦次男が仁品王政庁を担うものの、スケールダウンします。
もちろん「保高見熱躬」の名も「ひかるくん」の名も政権メンバーからはなくなります。
いままで、開拓で華やいだイメージの仁品王の物語は急に曇天となります。
しかし、にもかかわらず、この時、政権の中心にいたはずの「ひかるくん」の記述が一切ないのです。「仁品王の義理の兄」、「若王子の伯父」、「妹耶姫の実兄」の「ひかるくん」です。
この政局難の中、もっとも頼れるはずの人が一切語られないのですが、「安曇の古代」の著者の仁科宗一郎氏はこのことを挙げ、おそらく「ひかるくん」は「保高見熱躬」側についたため、大町の仁科氏の記録書である仁科濫觴記には登場しなくなったのではないかと推察しています。
確かに、「仁品王」と「保高見熱躬(ほたかみのあつみ)」との溝は、拡大政策を選択する「仁品王」と、民への過剰な負担を阻止したい「保高見熱躬」との溝であって、そうであれば、常に民と共にあった「ひかるくん」であれば「保高見熱躬」側につくことも十分考えられる選択です。
この、「仁品王」と「保高見熱躬」との最後の確執は、ハッピーエンド好きな僕としては残念な結果でした。
しかし、「信府統記」の元ネタが「仁科濫觴記」であるならば、信府統記やほかの民話の終わりが「ひかるくん」が犀龍の背中に乗ってどこかに消えてしまうという終わり方であるのは、治水を終えた後、白水郎日光(あまのひかる)の記述が一切なくなるという点からも類似性を感じます。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
いままで、開拓で華やいだイメージの仁品王の物語は急に曇天となります。
しかし、にもかかわらず、この時、政権の中心にいたはずの「ひかるくん」の記述が一切ないのです。「仁品王の義理の兄」、「若王子の伯父」、「妹耶姫の実兄」の「ひかるくん」です。
この政局難の中、もっとも頼れるはずの人が一切語られないのですが、「安曇の古代」の著者の仁科宗一郎氏はこのことを挙げ、おそらく「ひかるくん」は「保高見熱躬」側についたため、大町の仁科氏の記録書である仁科濫觴記には登場しなくなったのではないかと推察しています。
確かに、「仁品王」と「保高見熱躬(ほたかみのあつみ)」との溝は、拡大政策を選択する「仁品王」と、民への過剰な負担を阻止したい「保高見熱躬」との溝であって、そうであれば、常に民と共にあった「ひかるくん」であれば「保高見熱躬」側につくことも十分考えられる選択です。
この、「仁品王」と「保高見熱躬」との最後の確執は、ハッピーエンド好きな僕としては残念な結果でした。
しかし、「信府統記」の元ネタが「仁科濫觴記」であるならば、信府統記やほかの民話の終わりが「ひかるくん」が犀龍の背中に乗ってどこかに消えてしまうという終わり方であるのは、治水を終えた後、白水郎日光(あまのひかる)の記述が一切なくなるという点からも類似性を感じます。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月16日
検索 仁科濫觴記3 <泉小太郎伝説の実際(7)>
この「ひかるくん」の事業が仁科濫觴記のなかで、記述されていきますので、すこし仁科濫觴記の骨子だけを紹介します。
「仁品王」(にしなおう)という皇族が、都から安曇野開拓のために派遣されるところから物語ははじまります。「仁品王」は崇神天皇の末子で、垂仁天皇の末弟で、景行天皇の叔父にあたります。およそ4世紀くらいの古墳時代の人物だと思われます。(このあたりの検証は「安曇の古代」において仁科宗一郎氏が詳細に行っていますので省きます。)

「仁品王」は、最重臣の「保高見熱躬(ほたかみのあつみ)」をはじめ、開拓に必要と思われる各技能集団を引き連れ、この地に赴任してきます。
そして、政庁として今の長野県大町市の天王寺にあたるところに館を構えて開拓を推し進めます。そのため、この大町は王町(おうまち)と呼ばれます。
この後、「ひかる」の治水の表記がなされていきますが、省略して下記に述べます。
①この地区は湖水の底などではなかったものの、大雨が続く時には水嵩
が増し氾濫して湖のようになって民を苦しめていた。
②この地を開拓しようと都から出向いた仁品王が、従臣のなかから治水大臣に「九頭子」(くずこ 人名)を任命する。
③「九頭子」は「健男」の中から「ひかるくん」を選び、治水のための集団「白水郎」の長として「ひかるくん」を任じる。
④治水は「ひかるくん」の指揮により、健男を集めおこなわれた
⑤九頭子と「ひかるくん」は「征矩規峡(せいのりさわ)」を治水基地として治水を始める
⑥治水は数年にわたって行われたがその間にも「満水数度あり」と、氾濫が 何度かおきるなどの難工事であった
⑦さらに何年もかかり事業が成就すると川幅が広くなり、流れも滞ることがなくなり村里の民も豊穣に喜んだ
この中には、しごくまともな、治水事業の経過報告が書かれています。
この表記がなぜ、犀龍にのって堤を破って、安曇野盆地を開拓したという話にまで盛られていくかは、人間のエンターテイメントのサガでしょう。
こうやって歴史が民話になっていきます。
ちなみにこの治水大臣に任じられたのが「九頭子(くずこ)」という人物であったため、後世に戸隠神社の九頭竜大社と結び付けられ信府統記(しんぷとうき)では「泉小太郎」の父親が「白龍王」となったと思われます。ひょっとすると戸隠神社の九頭竜大社は祖霊としてまつられたこの「九頭子」がはじまりかもしれません。
また、「ひかるくん」の治水基地である「征矩規峡(せいのりさわ)」が「尾入沢(おのいりさわ)」になったのではないかと思います。
信府統記(しんぷとうき)の泉小太郎伝説の中では、この「尾入沢」で、小太郎は母親の犀龍と出会い、湖を破り開墾することになります。
歴史の民話化ってこんな感じなのかと、元となる正確な古文書と民話を時代を経た現代において、並列に読むとよくわかります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月15日
検索 仁科濫觴記2 <泉小太郎伝説の実際(6)>
仁科濫觴記(にしならんしょうき)によると泉小太郎のモデルは「白水郎日光」という実在の(と思われる)人物です。
後世に繰り返される写本のなかで誤写され「白水郎日光」が中世的な名前である「泉小太郎」とされてしまいます。(安曇の古代 新撰仁科記 の泉小太郎考 より)
まず、「白水郎日光」の意味がわからないため「白水光郎」と誤写され
「白水」が(縦書きなので)「泉」に変換され
「光郎」のほうは分解されて、(縦書きの楷書ではなく、行書、草書体なのでかなり崩されていますので)
小太郎になったそうです。

また仁科濫觴記の文中には名前に「日光」とあるため
もう一度日光をつけてしまい、
信府統記では「日光泉小太郎」とされたという変遷がありました。
さて、泉小太郎のモデルとなった「白水郎日光」ですが
これでなんと読むかといえば普通は「はくすいろうにっこう」でしょう。
しかし実際は
「あま ひかる(もしくは、あまのひかる)」と読みます。
「白水郎」は、どう読んでも「はくすいろう」と読めるのですが
平安時代の百科事典「和名類聚抄」には「あま」という呼び名で載っているそうです。
「あま」とは「海女」あるいは「海人」で、
古代では「あま」は、治水等を行う海洋部族もしくはその技術集団でした。
つまり、役職を表す名前の「白水郎」がついた「日光(ひかる)」で
泉小太郎のモデルとなった人物はあまの「ひかる」。
注)実際は「日光」とかいて「ひかる」ですが、
日光東照宮以降、「日光」をどう読んでも「にっこう」としか読めなくなってしまっているため
あえて「ひかるくん」と表記していきます。(あくまで名前なので 「くん」づけで)
治水技術をもつ専門技能集団「白水郎」(あま と読む)の一員「日光」
「大工の源さん」と同じような「あまの ひかる くん」です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
後世に繰り返される写本のなかで誤写され「白水郎日光」が中世的な名前である「泉小太郎」とされてしまいます。(安曇の古代 新撰仁科記 の泉小太郎考 より)
まず、「白水郎日光」の意味がわからないため「白水光郎」と誤写され
「白水」が(縦書きなので)「泉」に変換され
「光郎」のほうは分解されて、(縦書きの楷書ではなく、行書、草書体なのでかなり崩されていますので)
小太郎になったそうです。

また仁科濫觴記の文中には名前に「日光」とあるため
もう一度日光をつけてしまい、
信府統記では「日光泉小太郎」とされたという変遷がありました。
さて、泉小太郎のモデルとなった「白水郎日光」ですが
これでなんと読むかといえば普通は「はくすいろうにっこう」でしょう。
しかし実際は
「あま ひかる(もしくは、あまのひかる)」と読みます。
「白水郎」は、どう読んでも「はくすいろう」と読めるのですが
平安時代の百科事典「和名類聚抄」には「あま」という呼び名で載っているそうです。
「あま」とは「海女」あるいは「海人」で、
古代では「あま」は、治水等を行う海洋部族もしくはその技術集団でした。
つまり、役職を表す名前の「白水郎」がついた「日光(ひかる)」で
泉小太郎のモデルとなった人物はあまの「ひかる」。
注)実際は「日光」とかいて「ひかる」ですが、
日光東照宮以降、「日光」をどう読んでも「にっこう」としか読めなくなってしまっているため
あえて「ひかるくん」と表記していきます。(あくまで名前なので 「くん」づけで)
治水技術をもつ専門技能集団「白水郎」(あま と読む)の一員「日光」
「大工の源さん」と同じような「あまの ひかる くん」です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月14日
検索 仁科濫觴記1 <泉小太郎伝説の実際(5)>
検索「仁科濫觴記」(にしならんしょうき)
『仁科濫觴記 (ウィキペディアより)』
『仁科濫觴記(にしならんしょうき)は、崇神天皇の時代から弘仁までのおよそ1000年間における、古代の仁科氏の歴史。信濃国(長野県)安曇平の歴史や、地名の起こりに加え、部分的に中央政権の動向にも触れられている。著者は不明で、制作年代も平安時代初期に始まり江戸時代の完成になると考えられている。
この地域の記録としても知られる信府統記が、おとぎ話的な要素を多く含み、事件の背景年代もあいまいであるのに対し、あくまでも人間の歴史として時間軸に置いて記述しようとしている態度が一貫しており、また不確実な情報を極力少なくしようとしている点が、記録の信憑性を高めている、と考えられている。創作童話「たつのたろう」のモデルとなった民話の一つ泉小太郎伝説や、八面大王伝説など、松本・安曇平に伝わる伝承の元となった「史実」に触れることができる。』
とあります。
仁科濫觴記は 仁科宗一郎氏の著書『安曇の古代』に全文がのっており、その中で丁寧に検証されています。
さらにその検証の中で、仁科氏は山中で古墳も発見しています。名著ですので手に取る機会がありましたら
是非読んでみてください。
さて
この仁科濫觴記は、安曇野の北にあたる大町にいた豪族「仁科氏」のおこり(濫觴)を記録したもので大町にある国宝「仁科神明宮」にも関連のある一族の記録です。
国宝 仁科神明宮

仁科濫觴記(にしならんしょうき)には、この仁科神明宮の由来のほか、大町の歴史、穂高神社の創立、古代の政権交代の様子、ヤマトタケル東征の報を受けたこの地の対応の様子、仏教の伝来、八面大王伝説のもとになる説話、坂上田村麿伝説のもとになる説話、鼠族伝説の元になる説話など、この地方では各地に残る民話、伝説の元ネタになる説話の数々が記録されています。そのなかでも、「治水」に関する記述は重要なことであったのか、仁科濫觴記の冒頭からはじまり、その中で「泉小太郎」のモデルとなった人物が語られます。
仁科濫觴記の現代語訳 全文は下記のブログを参照ください
(球わかば さん よく晴れた雨の日に。現代語訳『仁科濫觴記』(全文))
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
『仁科濫觴記 (ウィキペディアより)』
『仁科濫觴記(にしならんしょうき)は、崇神天皇の時代から弘仁までのおよそ1000年間における、古代の仁科氏の歴史。信濃国(長野県)安曇平の歴史や、地名の起こりに加え、部分的に中央政権の動向にも触れられている。著者は不明で、制作年代も平安時代初期に始まり江戸時代の完成になると考えられている。
この地域の記録としても知られる信府統記が、おとぎ話的な要素を多く含み、事件の背景年代もあいまいであるのに対し、あくまでも人間の歴史として時間軸に置いて記述しようとしている態度が一貫しており、また不確実な情報を極力少なくしようとしている点が、記録の信憑性を高めている、と考えられている。創作童話「たつのたろう」のモデルとなった民話の一つ泉小太郎伝説や、八面大王伝説など、松本・安曇平に伝わる伝承の元となった「史実」に触れることができる。』
とあります。
仁科濫觴記は 仁科宗一郎氏の著書『安曇の古代』に全文がのっており、その中で丁寧に検証されています。
さらにその検証の中で、仁科氏は山中で古墳も発見しています。名著ですので手に取る機会がありましたら
是非読んでみてください。
さて
この仁科濫觴記は、安曇野の北にあたる大町にいた豪族「仁科氏」のおこり(濫觴)を記録したもので大町にある国宝「仁科神明宮」にも関連のある一族の記録です。
国宝 仁科神明宮

仁科濫觴記(にしならんしょうき)には、この仁科神明宮の由来のほか、大町の歴史、穂高神社の創立、古代の政権交代の様子、ヤマトタケル東征の報を受けたこの地の対応の様子、仏教の伝来、八面大王伝説のもとになる説話、坂上田村麿伝説のもとになる説話、鼠族伝説の元になる説話など、この地方では各地に残る民話、伝説の元ネタになる説話の数々が記録されています。そのなかでも、「治水」に関する記述は重要なことであったのか、仁科濫觴記の冒頭からはじまり、その中で「泉小太郎」のモデルとなった人物が語られます。
仁科濫觴記の現代語訳 全文は下記のブログを参照ください
(球わかば さん よく晴れた雨の日に。現代語訳『仁科濫觴記』(全文))
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月14日
泉小太郎って?3 <泉小太郎伝説の実際(4)>
この泉小太郎の伝承に関する地名もこの地にはいくつも残っており
民話とともにこの地の古代の開発物語として人々の想像をかきたててくれています。
ただ、この安曇野が湖だったということは、
地質的なボーリング調査の結果
一度もそのようなことはなかったことが判明していますし
突き破ったといわれる山清路も川の浸食により
今の状態になったことが判明しています。
では、これは昔の人の全くの想像物語かといわれれば違います。
この物語は、過去にここを開拓した人々の治水事業が伝承され民話化したものです。
なぜそれがわかるかといえば、
今引用した江戸時代にまとめられた「信府統記」にはその元にあたる古文書が存在し
そこにはより記録的に「泉小太郎」のもとになった人物に関しての記述があるのです。
それが古文書「仁科濫觴記(にしならんしょうき)」です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
民話とともにこの地の古代の開発物語として人々の想像をかきたててくれています。
ただ、この安曇野が湖だったということは、
地質的なボーリング調査の結果
一度もそのようなことはなかったことが判明していますし
突き破ったといわれる山清路も川の浸食により
今の状態になったことが判明しています。
では、これは昔の人の全くの想像物語かといわれれば違います。
この物語は、過去にここを開拓した人々の治水事業が伝承され民話化したものです。
なぜそれがわかるかといえば、
今引用した江戸時代にまとめられた「信府統記」にはその元にあたる古文書が存在し
そこにはより記録的に「泉小太郎」のもとになった人物に関しての記述があるのです。
それが古文書「仁科濫觴記(にしならんしょうき)」です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月13日
泉小太郎って?2 <泉小太郎伝説の実際(3)>
「泉小太郎伝説」 『信府統記より』
『景行天皇12年まで、松本のあたりは山々から流れてくる水を湛える湖であった。その湖には犀竜が住んでおり、東の高梨の池に住む白竜王との間に一人の子供をもうけた。名前を日光泉小太郎という。しかし小太郎の母である犀竜は、自身の姿を恥じて湖の中に隠れてしまう。
筑摩郡中山の産ヶ坂で生まれ、放光寺で成人した小太郎は母の行方を捜し、尾入沢で再会を果たした。そこで犀竜は自身が建御名方神の化身であり、子孫の繁栄を願って顕現したことを明かす。そして、湖の水を流して平地とし、人が住める里にしようと告げた。小太郎は犀竜に乗って山清路の巨岩や久米路橋の岩山を突き破り、日本海へ至る川筋を作った』 泉小太郎は母である犀龍の背中にのり琵琶湖かそれ以上の大きな湖の堤を破ってこの地を水田にしたあと、日本海まで突き抜けていくという壮大な物語です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
『景行天皇12年まで、松本のあたりは山々から流れてくる水を湛える湖であった。その湖には犀竜が住んでおり、東の高梨の池に住む白竜王との間に一人の子供をもうけた。名前を日光泉小太郎という。しかし小太郎の母である犀竜は、自身の姿を恥じて湖の中に隠れてしまう。
筑摩郡中山の産ヶ坂で生まれ、放光寺で成人した小太郎は母の行方を捜し、尾入沢で再会を果たした。そこで犀竜は自身が建御名方神の化身であり、子孫の繁栄を願って顕現したことを明かす。そして、湖の水を流して平地とし、人が住める里にしようと告げた。小太郎は犀竜に乗って山清路の巨岩や久米路橋の岩山を突き破り、日本海へ至る川筋を作った』 泉小太郎は母である犀龍の背中にのり琵琶湖かそれ以上の大きな湖の堤を破ってこの地を水田にしたあと、日本海まで突き抜けていくという壮大な物語です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月12日
泉小太郎って?1 <泉小太郎伝説の実際(2)>
「泉小太郎」
安曇野、松本平に伝わる「泉小太郎伝説」を
児童文学者の松谷みよ子氏が
一時はアニメ映画化され
一番有名なのは

「泉小太郎伝説」は
それが江戸時代に松本城主の指示により
「信府統記」としてまとめられました。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
安曇野、松本平に伝わる「泉小太郎伝説」を
児童文学者の松谷みよ子氏が
50年前にまとめ
童話「たつのこたろう」として出版しました
一時はアニメ映画化され
紙芝居 演劇にもなっています。
一番有名なのは
「ぼうや~よいこだねんねしな~」で知られる
日本昔ばなしのオープニングに登場する
日本昔ばなしのオープニングに登場する
彼が
「たつのこたろう」です。
「たつのこたろう」です。

「泉小太郎伝説」は
安曇野 大町 松本を中心とした
長野県の「中信地方」の各地に伝えられており
長野県の「中信地方」の各地に伝えられており
それが江戸時代に松本城主の指示により
「信府統記」としてまとめられました。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月11日
歴史発見!泉小太郎伝説 <泉小太郎伝説の実際(1)>
はじめに
一生に一度とも言える
一生に一度とも言える
歴史的大発見をしてしまいました。
今、そんな感覚があります。
さまざまな経緯の中でここ数年、
今回のテーマである「泉小太郎伝説」が気になり
調べていました。
さまざまな経緯の中でここ数年、
今回のテーマである「泉小太郎伝説」が気になり
調べていました。
「泉小太郎伝説」は「たつのこたろう」としても知られ、
僕の住んでいた長野県の中央部「中信地区」に伝わる民話です。
僕の住んでいた長野県の中央部「中信地区」に伝わる民話です。
気になり始めると自分が納得するまでやめられないクセのある僕は
かれこれ10年にわたって調査していました。
かれこれ10年にわたって調査していました。
特に進展はなかったのですが、
2年前に「田沢神明宮」を調べ始めたら
次々に新事実が浮かび上がり、
2年前に「田沢神明宮」を調べ始めたら
次々に新事実が浮かび上がり、
最終的にはおそらくまだ誰も唱えていないある事実に
突き当たりました。
皆さんは一生に一度と思えるほどの
発見をしたことが
ありますか。
誰も気が付いていない事実が
次々に明るみになってくるのです。
この事実を誰かに伝えずにはいられない。
そんな思いをこめたブログです。
僕の発見したこの地の歴史に、胸を熱くされると思います。
突き当たりました。
皆さんは一生に一度と思えるほどの
発見をしたことが
ありますか。
誰も気が付いていない事実が
次々に明るみになってくるのです。
この事実を誰かに伝えずにはいられない。
そんな思いをこめたブログです。
僕の発見したこの地の歴史に、胸を熱くされると思います。