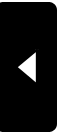2022年02月23日
泉小太郎伝説の実際 目次
目次
1年目
歴史発見!泉小太郎伝説
泉小太郎って ?
検索 仁科濫觴記
スタートライン!いよいよ泉小太郎伝説の探索が始まります。
検索 穂高神社
検索 「サイって?」
検索 光城山(ひかるじょうやま)
検索 田沢神明宮
検索 豊科図書館
検索 田沢神明宮縁起
したくなかった検索 「犀の角をもとめて」
検索 知りたくなかった「天文年間」
検索 ふたたび「犀の角」を探して
検索 古代の治水工事
検索 信玄堤
泉小太郎伝説を調べまくる 1年目のまとめ
2年目
検索 やっぱり「犀の角」はどこ?
検索 竜宝の墓 入明寺
検索 ふりだしの犀の角
検索 武田軍その後
検索 仏崎観音寺
検索 信府統記
コラム1 泉小太郎とお船祭り
検索 放光寺
検索 廃仏毀釈
検索 二つの「信濃日光」放光寺
検索 二つの「信濃日光」若澤寺(廃寺)
検索 川会神社
泉小太郎を調べまくる 2年目のまとめ
3年目
検索 農具川
検索 仁科神社
検索 海ノ口神社
検索 銅戈
コラム2 泉小太郎と道祖神 三九郎
検索 泉小太郎の開発地域
検索 ふたたび穂高神社
検索 犀の角をもとめて
泉小太郎を調べまくる 三年目のまとめ
1年目
歴史発見!泉小太郎伝説
泉小太郎って ?
検索 仁科濫觴記
スタートライン!いよいよ泉小太郎伝説の探索が始まります。
検索 穂高神社
検索 「サイって?」
検索 光城山(ひかるじょうやま)
検索 田沢神明宮
検索 豊科図書館
検索 田沢神明宮縁起
したくなかった検索 「犀の角をもとめて」
検索 知りたくなかった「天文年間」
検索 ふたたび「犀の角」を探して
検索 古代の治水工事
検索 信玄堤
泉小太郎伝説を調べまくる 1年目のまとめ
2年目
検索 やっぱり「犀の角」はどこ?
検索 竜宝の墓 入明寺
検索 ふりだしの犀の角
検索 武田軍その後
検索 仏崎観音寺
検索 信府統記
コラム1 泉小太郎とお船祭り
検索 放光寺
検索 廃仏毀釈
検索 二つの「信濃日光」放光寺
検索 二つの「信濃日光」若澤寺(廃寺)
検索 川会神社
泉小太郎を調べまくる 2年目のまとめ
3年目
検索 農具川
検索 仁科神社
検索 海ノ口神社
検索 銅戈
コラム2 泉小太郎と道祖神 三九郎
検索 泉小太郎の開発地域
検索 ふたたび穂高神社
検索 犀の角をもとめて
泉小太郎を調べまくる 三年目のまとめ
2022年02月23日
検索 田沢神明宮3 <泉小太郎伝説の実際(19)>
僕の想像していた、古代の土木機具そのものが目の前に登場したのです。

写真をみてください。
「船石」と呼ぶには不恰好ではありませんか?
なんだか船の先の舳(へさき)の部分が欠けているような印象を受けます。

するとこの船石の説明が横にきちんとありました。
船石の由来の写真

『安曇野開拓の祖 日光泉小太郎、神明宮(天照皇大神)の神恩に報いんが為に天の磐舟を造りて献げ置きし処 何時しか石の舟に変ぜり 天文年間 心なき者 此の舟石に穴をうかち砕かんとしたところ神罰に依り其の者俄かに死せりと伝承せらる』
とあります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
(参照 検索 「サイって?」2)

写真をみてください。
「船石」と呼ぶには不恰好ではありませんか?
なんだか船の先の舳(へさき)の部分が欠けているような印象を受けます。

するとこの船石の説明が横にきちんとありました。
船石の由来の写真

『安曇野開拓の祖 日光泉小太郎、神明宮(天照皇大神)の神恩に報いんが為に天の磐舟を造りて献げ置きし処 何時しか石の舟に変ぜり 天文年間 心なき者 此の舟石に穴をうかち砕かんとしたところ神罰に依り其の者俄かに死せりと伝承せらる』
とあります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月22日
検索 田沢神明宮2 <泉小太郎伝説の実際(18)>
田沢神明宮は泉小太郎こと「ひかるくん」が創建したというのです。
僕はひかるくんの偉業を思いつつ参拝しました。
深い森しかない暗い印象すらうける場所で、とりわけて珍しいものもなく、
よくあるその村の神社といった感じです。どちらかといえば寂れているといった印象です。
でも、僕の目には全く別に映ります。
たぶん、「ひかるくん」は、この光城山に幾度も登り、
治水計画のグランドラインを立てたのではないでしょうか。
そして、その治水工事の始まる時期もしくは完了時に
この山を御神体(もしくは「よりしろ」)として祀ったのではないでしょうか。
輝かしい頃のひかるくんがイメージされます。
苦楽をともにした「健男たち」に囲まれて、祝い、笑い、肩をたたきあっている。
豊穣を称えてみんなで酒を酌み交わしている。
ああ、ひかるくんは実在した。そう思える瞬間でした。
そして、次の発見から想像だにしていなかった展開が始まるのです。
それは、この神明宮にはなんと舟石とよばれる巨石があったのです!!!
それがこの写真

思わず!!! 「犀だ!!!」と叫んでしまいました。
しかも名前が「船石」
僕の想像していた、古代の土木機具そのものが目の前に登場したのです。
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月22日
検索 田沢神明宮1 <泉小太郎伝説の実際(17)>
光城山の麓で発見した田沢神明宮

立てかけられた由緒書には泉小太郎創建とあります。

マップ 田沢神明宮
泉小太郎が祀られているのではなく
泉小太郎が創建としているところにも
この神社の重要さを感じます。
「日光泉小太郎」が江戸時代以降、日光東照宮にひきずられて
どう読んでも「にっこういずみこたろう」としか
読めなくなってしまっていますが
泉小太郎の本名が「ひかる」であったのを解き明かしたのは仁科濫觴記のみであり
それを読み解いた「安曇の古代」著者 仁科宗一郎さんであるのです。
その「ひかる」の名の「光城山(ひかるじょうやま)」の麓に
この 泉小太郎が創建したという「田沢神明宮」はあるのです。
ただ、ここに至っても泉小太郎氏が「ひかる」という名前だったことを書いてある文章はなく、(光城山のふもとにあるにも関わらずです)ひょっとして、ネットでは(ウィキペディアでは、あるいは仁科濫觴記研究者では)よく知られた話でも、他の人はまったく知らない事実なのかもしれないです(だとすると信府統記の悪影響ですが)
いちどこの地のかたと話す機会がありましたが
「光」と書いて「ひかり」ではなく「ひかる」と読むことに違和感を感じていました
この地の名は、たしかに豊科光(とよしなひかる)と明科光(あかしなひかる)に
別れていますが、今の地番になる前は、この地は「光」(ひかる)でした。
この「ひかる」問題は早めに是正すべき問題だと思います。「信府統記」および伝承で「あまのひかる」という名前が、中世的な「日光泉小太郎」という名前になってしまい、しかもあまりに有名な「日光(にっこう)東照宮」が、あったため、当の「光」地区に住む人、あるいはその地番所有の豊科町、明科町でさえ、ひかるの名前の由来が 白水郎日光(あまのひかる)なのだということを知らないのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら

立てかけられた由緒書には泉小太郎創建とあります。

マップ 田沢神明宮
泉小太郎が祀られているのではなく
泉小太郎が創建としているところにも
この神社の重要さを感じます。
「日光泉小太郎」が江戸時代以降、日光東照宮にひきずられて
どう読んでも「にっこういずみこたろう」としか
読めなくなってしまっていますが
泉小太郎の本名が「ひかる」であったのを解き明かしたのは仁科濫觴記のみであり
それを読み解いた「安曇の古代」著者 仁科宗一郎さんであるのです。
その「ひかる」の名の「光城山(ひかるじょうやま)」の麓に
この 泉小太郎が創建したという「田沢神明宮」はあるのです。
ただ、ここに至っても泉小太郎氏が「ひかる」という名前だったことを書いてある文章はなく、(光城山のふもとにあるにも関わらずです)ひょっとして、ネットでは(ウィキペディアでは、あるいは仁科濫觴記研究者では)よく知られた話でも、他の人はまったく知らない事実なのかもしれないです(だとすると信府統記の悪影響ですが)
いちどこの地のかたと話す機会がありましたが
「光」と書いて「ひかり」ではなく「ひかる」と読むことに違和感を感じていました
この地の名は、たしかに豊科光(とよしなひかる)と明科光(あかしなひかる)に
別れていますが、今の地番になる前は、この地は「光」(ひかる)でした。
この「ひかる」問題は早めに是正すべき問題だと思います。「信府統記」および伝承で「あまのひかる」という名前が、中世的な「日光泉小太郎」という名前になってしまい、しかもあまりに有名な「日光(にっこう)東照宮」が、あったため、当の「光」地区に住む人、あるいはその地番所有の豊科町、明科町でさえ、ひかるの名前の由来が 白水郎日光(あまのひかる)なのだということを知らないのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月21日
検索 光城山(ひかるじょうやま)2 <泉小太郎伝説の実際(16)>
光城山がもし「ひかるくん」と関係しているのならば
山の南側の麓になにかがあるに違いないと思っていました。
なぜなら以前訪れた国宝の仁科親明宮が山の南側にあったからです。
神社はたいてい 南か東を向いているものです。
ただ、当時は(3年ほど前)グーグルマップで調べてもそれらしいものはありません。
しかし僕はきっと小さな祠でもあるに違いないと思い、誘われるように光城山の南
に向かって車を走らせました。
すると、なんてことでしょう。
本当に導かれたようにというか、拍子抜けなほどあっさりと痕跡を見つけました。
それは配置的には仁科神明宮に似た配置にある田沢神明宮という神社です。
田沢神明宮!!!(しかも「神明宮」!)

笑ってしまうほどあっさりと見つかりました。
車を降りて神社の由緒の書いた看板をみると

読みにくいのですが冒頭に
「景行天皇十二年九月十六日、日光泉小太郎創立」とあります。
なんとこの神社は、泉小太郎が建てたというのです。
この時の僕の体の震えをお伝えしたいくらいです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
山の南側の麓になにかがあるに違いないと思っていました。
なぜなら以前訪れた国宝の仁科親明宮が山の南側にあったからです。
神社はたいてい 南か東を向いているものです。
ただ、当時は(3年ほど前)グーグルマップで調べてもそれらしいものはありません。
しかし僕はきっと小さな祠でもあるに違いないと思い、誘われるように光城山の南
に向かって車を走らせました。
すると、なんてことでしょう。
本当に導かれたようにというか、拍子抜けなほどあっさりと痕跡を見つけました。
それは配置的には仁科神明宮に似た配置にある田沢神明宮という神社です。
田沢神明宮!!!(しかも「神明宮」!)

笑ってしまうほどあっさりと見つかりました。
車を降りて神社の由緒の書いた看板をみると

読みにくいのですが冒頭に
「景行天皇十二年九月十六日、日光泉小太郎創立」とあります。
なんとこの神社は、泉小太郎が建てたというのです。
この時の僕の体の震えをお伝えしたいくらいです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月21日
検索 光城山(ひかるじょうやま)1 <泉小太郎伝説の実際(15)>
「犀型の巨石」あるいは「角型の巨石」の検索はうまくいきませんでした。
各地に巨石はあるもののそれと思うものがないのです。
僕は犀型の巨石の探索をあきらめ別の方向から攻めることにしました。
仁科濫觴記では、泉小太郎の名を「日光」(ひかる)としていました。
信府統記でも「日光泉小太郎」としています。
おそらく、江戸時代には「日光」と書いて「にっこう」としか
音読されていなかったと考えられますが
「日光泉小太郎」の本当の名は
「ひかるくん」であると述べました。 ( 検索 仁科濫觴記 2 参照)
さて
「ひかる」という名前を聞いて、この地区に住む人ならピンとくる地名がひとつあります。
それが「光城山」(ひかるじょうやま)です。
『光城山』 (ウィキペディアより)
『光城山(ひかるじょうやま)は、長野県安曇野市豊科にある山である。標高911.7m。鎌倉時代に海野氏の支族が築いた光城(仁場城)に由来。山頂には、車でも行くことができる。豊科光からの登山道は桜が植えられている。』
とあり、確かに桜の名所ともなっているハイキングにはもってこいの場所です。光城山からの風景です。

光城山 マップ
僕は、「ひかる」という名前を知ってから、この山の名前の由来をネット上で調べましたが
「海野氏の系譜のなかで、このあたりは光氏が治めていた。そこから、光城山となった」というものが発見されました。
でも、この説明には僕は違和感を感じていました。「光山という名前が元からあって、そこを治めたのでそこから名前をとって光氏にした」のではないかと考えたからです。
実際にさらに調べてみると、海野氏はさかのぼること平安の時代からある氏族で、鎌倉時代に支族として「幸氏(ゆきし)」が分岐して、そのまた支族として6人兄弟が生まれ、長男は幸氏を継ぎ、残りの五人はそれぞれもともと松本、安曇野地区にあった地名をとり、会田氏、塔原氏、田沢氏、刈屋原氏、光氏と分枝するとありました
やはり「ひかる」自体の名がもともとあり、そこに来た海野一族が、光氏と名乗ったというのが正解だということがわかります。
「ひかる」の名を知った瞬間、ここに運命の何かを感じ高鳴る胸を抱きます。僕はいてもたってもいられず、すぐに光城山に向かいました。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
各地に巨石はあるもののそれと思うものがないのです。
僕は犀型の巨石の探索をあきらめ別の方向から攻めることにしました。
仁科濫觴記では、泉小太郎の名を「日光」(ひかる)としていました。
信府統記でも「日光泉小太郎」としています。
おそらく、江戸時代には「日光」と書いて「にっこう」としか
音読されていなかったと考えられますが
「日光泉小太郎」の本当の名は
「ひかるくん」であると述べました。 ( 検索 仁科濫觴記 2 参照)
さて
「ひかる」という名前を聞いて、この地区に住む人ならピンとくる地名がひとつあります。
それが「光城山」(ひかるじょうやま)です。
『光城山』 (ウィキペディアより)
『光城山(ひかるじょうやま)は、長野県安曇野市豊科にある山である。標高911.7m。鎌倉時代に海野氏の支族が築いた光城(仁場城)に由来。山頂には、車でも行くことができる。豊科光からの登山道は桜が植えられている。』
とあり、確かに桜の名所ともなっているハイキングにはもってこいの場所です。光城山からの風景です。

光城山 マップ
僕は、「ひかる」という名前を知ってから、この山の名前の由来をネット上で調べましたが
「海野氏の系譜のなかで、このあたりは光氏が治めていた。そこから、光城山となった」というものが発見されました。
でも、この説明には僕は違和感を感じていました。「光山という名前が元からあって、そこを治めたのでそこから名前をとって光氏にした」のではないかと考えたからです。
実際にさらに調べてみると、海野氏はさかのぼること平安の時代からある氏族で、鎌倉時代に支族として「幸氏(ゆきし)」が分岐して、そのまた支族として6人兄弟が生まれ、長男は幸氏を継ぎ、残りの五人はそれぞれもともと松本、安曇野地区にあった地名をとり、会田氏、塔原氏、田沢氏、刈屋原氏、光氏と分枝するとありました
やはり「ひかる」自体の名がもともとあり、そこに来た海野一族が、光氏と名乗ったというのが正解だということがわかります。
「ひかる」の名を知った瞬間、ここに運命の何かを感じ高鳴る胸を抱きます。僕はいてもたってもいられず、すぐに光城山に向かいました。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月20日
検索 「サイって?」2 <泉小太郎伝説の実際(14)>
「犀」が動物の「サイ」ではなかったとすれば何だったのでしょうか。
僕は泉小太郎伝説の中に出てくる
「犀龍」の背中に乗って堤をつきやぶるシーンから
「犀」とは治水工事で使われる掘削機のようなものではなかったかと考えたのです。
古代に使われた材質とすれば、木か石かと思い、僕は下図のように治水用の土木機具「犀」をイメージしました。

鉄などはあったとしても、まだ希少だったと思われるので、「犀型」もしくは「つの型」の巨石が使われて、土木工事をしたのではと思ったのです。
そこで、まずは現代に使われている土木機具、農耕機具を検索してみましたが、「犀」というものは検索できませんでした。
次に、古代の土木機具についても調べてみようとおもったのですが僕の力では見つけることができませんでした。
ただ、実際に治水工事は行われたので「犀」ではなくとも、何らかの大型機具が使われたのは間違いないと思われます。穂高神社に伝わる「お船祭り」がその大型土木機具の治水工事が形を変えたものかとも思ったり、全国各地にある「天の磐船(いわふね)」信仰は古代の土木機械の名残りではないかとも考えましたが、思うように検索ができませんでした。
とにかく、古代に治水工事が行われていたとしたら、何かしらの材料を使ったはずです。僕はそれを犀型の巨石と考えて、巨石にまつわる場所を検索したのですが、これという決定打は見つけることが出来ませんでした。
また、長野県内には「犀」もしくは「才」の名のつく場所が結構あります。
関連もあるかといろいろ探りましたが思うような発見は見出すことができませんでした。
そして、しばらくは「犀」の探索を休止しました。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
僕は泉小太郎伝説の中に出てくる
「犀龍」の背中に乗って堤をつきやぶるシーンから
「犀」とは治水工事で使われる掘削機のようなものではなかったかと考えたのです。
古代に使われた材質とすれば、木か石かと思い、僕は下図のように治水用の土木機具「犀」をイメージしました。

鉄などはあったとしても、まだ希少だったと思われるので、「犀型」もしくは「つの型」の巨石が使われて、土木工事をしたのではと思ったのです。
そこで、まずは現代に使われている土木機具、農耕機具を検索してみましたが、「犀」というものは検索できませんでした。
次に、古代の土木機具についても調べてみようとおもったのですが僕の力では見つけることができませんでした。
ただ、実際に治水工事は行われたので「犀」ではなくとも、何らかの大型機具が使われたのは間違いないと思われます。穂高神社に伝わる「お船祭り」がその大型土木機具の治水工事が形を変えたものかとも思ったり、全国各地にある「天の磐船(いわふね)」信仰は古代の土木機械の名残りではないかとも考えましたが、思うように検索ができませんでした。
とにかく、古代に治水工事が行われていたとしたら、何かしらの材料を使ったはずです。僕はそれを犀型の巨石と考えて、巨石にまつわる場所を検索したのですが、これという決定打は見つけることが出来ませんでした。
また、長野県内には「犀」もしくは「才」の名のつく場所が結構あります。
関連もあるかといろいろ探りましたが思うような発見は見出すことができませんでした。
そして、しばらくは「犀」の探索を休止しました。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月20日
検索 「サイって?」1 <泉小太郎伝説の実際(13)>

穂高神社にある泉小太郎像の「犀龍」(さいりゅう)のインパクトが強くて、はじめ「動物」の「サイ」を使って治水工事をしたのではないのかと仮説をたてました。
その後、動物の「サイ」の出生を探ってみましたが、中国以北の犀は絶滅していることもわかり、最終的には、古代の船を考えれば、サイを乗せて日本に上陸するなんてことは出来るわけがないという あたりまえの結論を得たのでした。
(ちなみに絶滅の要因は、角を妙薬と考え、皮を防具として使ったことによる乱獲が原因だったそうです。)
となると「犀」とはなんなのかということです。
この地に「犀」の名が伝わった時点では、すでに「犀」という漢字がつくられた中国にも「犀」はいなかったのです。
「犀」という何かがこの地に伝わったのでなければ「犀」という言葉がこの地に伝わることもなかったでしょうし
「犀龍」なんていう特殊な単語がこの地に残ることもなかったはずです。
「犀」という何らかのものの探索がはじまりました。
犀といえば「つの」が特徴的です。紙芝居ではたつのこ太郎は母親である「犀龍」を操り堤に何度も体当たりさせて切りひらき田畑を開拓します。
この風景は、まるで掘削機械が土砂を切り崩す風景に似ていませんか?
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月19日
検索 穂高神社3 <泉小太郎伝説の実際(12)>
それよりも僕は衝撃を受けたのは
この穂高神社にある像です。
この松本盆地、安曇野、大町地区の各地には数々のたつのこたろう(泉小太郎)像がありますが、ここの像は他の像とは大きく違います。
他の地域の像は次の写真のようなものです。

マップ 大町 小太郎広場にある泉小太郎像
それが穂高神社はこのような像なのです。
もう一度添付します。

マップ 穂高神社の泉小太郎像
泉小太郎のまたがるこれはなんでしょうか
私は初めて見た時、衝撃で
「あれ?龍じゃないの?」
「豚?いやいや犀(サイ)か」
たしかに信府統記をみても、ただの「龍」ではなくわざわざ「犀龍」とあります。
「犀龍」。よく考えてみると、いままでこんな単語聞いたこともありません。僕はこの像にかなりの違和感を覚えたのです。
どうしてわざわざ犀龍なのでしょうか。これでは、たつのこ太郎じゃなくて犀の子太郎です。
ここから、僕の関心は「犀」に移ってしまうのです。
「龍」じゃいけなかったのでしょうか。わざわざ「龍」ではなく「犀龍」ってことは「犀」に意味があるのではないでしょうか。「犀川」の名も不思議です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
この穂高神社にある像です。
この松本盆地、安曇野、大町地区の各地には数々のたつのこたろう(泉小太郎)像がありますが、ここの像は他の像とは大きく違います。
他の地域の像は次の写真のようなものです。

マップ 大町 小太郎広場にある泉小太郎像
それが穂高神社はこのような像なのです。
もう一度添付します。

マップ 穂高神社の泉小太郎像
泉小太郎のまたがるこれはなんでしょうか
私は初めて見た時、衝撃で
「あれ?龍じゃないの?」
「豚?いやいや犀(サイ)か」
たしかに信府統記をみても、ただの「龍」ではなくわざわざ「犀龍」とあります。
「犀龍」。よく考えてみると、いままでこんな単語聞いたこともありません。僕はこの像にかなりの違和感を覚えたのです。
どうしてわざわざ犀龍なのでしょうか。これでは、たつのこ太郎じゃなくて犀の子太郎です。
ここから、僕の関心は「犀」に移ってしまうのです。
「龍」じゃいけなかったのでしょうか。わざわざ「龍」ではなく「犀龍」ってことは「犀」に意味があるのではないでしょうか。「犀川」の名も不思議です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年02月19日
検索 穂高神社2 <泉小太郎伝説の実際(11)>
穂高神社の祭神の穂高見命(ほたかみのみこと)とは、仁科濫觴記(にしならんしょうき)に出てくる保高見熱躬(ほたかみのあつみ)だと思われます。仁科濫觴記の描く時代はちょうど、古墳時代から神社造営時代の変遷期であったため、仁品王家にまつわる人々の多くが神社として祀られているケースがあり、この穂高神社も保高見熱躬が祭神であると思われます。
さて、この穂高神社で今後の探索を大きくかえることになる別のテーマを発見することになるのです。実はこの発見が後々この泉小太郎伝説の驚くべき真実に僕をいざなうことになるのですが、この時には全く予想もしていませんでした。
さて、穂高神社の中を散策するとすぐに次の像を発見できます。
それがこの写真です。

この像とともに泉小太郎伝説の紹介された碑文があります。

この内容は泉小太郎って?2で掲載しましたので省略し、最後の一文だけ紹介します。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
さて、この穂高神社で今後の探索を大きくかえることになる別のテーマを発見することになるのです。実はこの発見が後々この泉小太郎伝説の驚くべき真実に僕をいざなうことになるのですが、この時には全く予想もしていませんでした。
さて、穂高神社の中を散策するとすぐに次の像を発見できます。
それがこの写真です。

この像とともに泉小太郎伝説の紹介された碑文があります。

この内容は泉小太郎って?2で掲載しましたので省略し、最後の一文だけ紹介します。
『又、小太郎の父白龍王は海津見神であり小太郎は穂高見神の化身といわれ治山治水の功績を称えております。(信府統記より)』
碑文の中に「泉小太郎は穂高見命の化身である」という説明があります。
この一文が掲載される理由となる穂高神社縁起をそのうち調べようと思っていますが、この一文だけでも「保高見熱躬」と「ひかるくん」のその後の関係の良好さは知ることができます。
碑文の中に「泉小太郎は穂高見命の化身である」という説明があります。
この一文が掲載される理由となる穂高神社縁起をそのうち調べようと思っていますが、この一文だけでも「保高見熱躬」と「ひかるくん」のその後の関係の良好さは知ることができます。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら