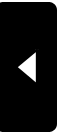2022年04月18日
検索 農具川2<泉小太郎伝説の実際(76)>
池田町の県道を走りながら東の山麓を望むと、高瀬川(農具川も含めて)の水位からずっと高地まで水田が広がっていることが見渡せます。ほぼ山の中腹まで水田が広がっているのですが、車で初めてこの場所を通った時に違和感を感じました。
「どのように水をあの高い位置まであげたのだろう」と不思議に思わずにはいられませんでした。
この高い水田地、どこから水をひいているのだろうとグーグルマップでしらべてみると
水路はずっと北の位置の農具川から取水されていることを発見します。
しかもある高さで山腹をほぼ真っ直ぐ、横一直線に水道が貫いていくのです。
この水路を一度サイクリングか ウォーキングで辿ってみたいという思いもあるのですが
コロナのため、まだ出来ていません。
非常に美しい古道もしくは古水道があるのではと思っています。
(観光資源としてもいいのではないかと思います。)
ある時、山腹にほぼ等高線にそって流れる水路を探るべく
車で辿れるところを何度か辿ってみました。
するとそこで仁科神明宮を発見したのです。
仁科神明宮マップ

以前から国宝仁科神明宮という看板は見ていましたが
その頃は歴史や神社などにも興味はありませんでしたから何気なしにみていました。
しかし農業用水路(どちらかといえば農業のほうに興味がありましたので)を
めぐるなかで農具川の支流である水路沿いに仁科神明宮を発見しました。
仁科神明宮のすぐ近くを流れる農具川水系取水の水路

その後、泉小太郎伝説を探るなかで川会神社に辿り着き
「川会」の川は 高瀬川とこの農業用水路に過ぎない農具川との合流地点という
ことを知った後は にわかに農具川に重大な内容が隠されていると感じられることと
なりました。
ひょっとすると
仁科神明宮も川会神社も 農業用水路の開拓時に創立された可能性があるのではないか。
そして、それはこの地の開発の祈念とともに、川のメンテナンスのために作られた神社では
ないかと考えられるのです。
この農具川の流域こそが
仁科濫觴記に書かれた「仁品王」が「九頭子」に命じた
開発計画の主要な計画ではなかったかとおもわれるのです。
仁品王が館を構え、中心地とした場所と農具川の水系を考えれば
非常にあり得る仮説だと思うのですがいかがでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
「どのように水をあの高い位置まであげたのだろう」と不思議に思わずにはいられませんでした。
この高い水田地、どこから水をひいているのだろうとグーグルマップでしらべてみると
水路はずっと北の位置の農具川から取水されていることを発見します。
しかもある高さで山腹をほぼ真っ直ぐ、横一直線に水道が貫いていくのです。
この水路を一度サイクリングか ウォーキングで辿ってみたいという思いもあるのですが
コロナのため、まだ出来ていません。
非常に美しい古道もしくは古水道があるのではと思っています。
(観光資源としてもいいのではないかと思います。)
ある時、山腹にほぼ等高線にそって流れる水路を探るべく
車で辿れるところを何度か辿ってみました。
するとそこで仁科神明宮を発見したのです。
仁科神明宮マップ

以前から国宝仁科神明宮という看板は見ていましたが
その頃は歴史や神社などにも興味はありませんでしたから何気なしにみていました。
しかし農業用水路(どちらかといえば農業のほうに興味がありましたので)を
めぐるなかで農具川の支流である水路沿いに仁科神明宮を発見しました。
仁科神明宮のすぐ近くを流れる農具川水系取水の水路

その後、泉小太郎伝説を探るなかで川会神社に辿り着き
「川会」の川は 高瀬川とこの農業用水路に過ぎない農具川との合流地点という
ことを知った後は にわかに農具川に重大な内容が隠されていると感じられることと
なりました。
ひょっとすると
仁科神明宮も川会神社も 農業用水路の開拓時に創立された可能性があるのではないか。
そして、それはこの地の開発の祈念とともに、川のメンテナンスのために作られた神社では
ないかと考えられるのです。
この農具川の流域こそが
仁科濫觴記に書かれた「仁品王」が「九頭子」に命じた
開発計画の主要な計画ではなかったかとおもわれるのです。
仁品王が館を構え、中心地とした場所と農具川の水系を考えれば
非常にあり得る仮説だと思うのですがいかがでしょうか。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月18日
検索 農具川1<泉小太郎伝説の実際(75)>
実はいままで省略してしまっていた部分になるのですが
僕はこの農具川及びその支流が仁品王が治水工事を命じて作らせた農業用水路ではないかと以前より考えて調査していました。
農具川水系のマップ
川の地図ですのでわかりづらいとは思いますが
この松本平、安曇平の北限にあたる木崎湖から
この地の東の山沿いを通る形で流れる川です。
往古より幾度も治水工事がなされているため
川筋の変遷は不明ですが
直線を含むルートであったり
等高線を意識したような標高まで計算された水路や
東側の水が不足がちな場所を遥か北で標高のたかい青木から取水するなど
農業用水路として開発されたものであることは理解していただけるかと思います。
農業用水は、昔から興味の対象で
泉小太郎の物語を知るのは10年前でしたが
農業用水の探究はずっと昔から行っており
その中でもこの農具川水系は興味をそそるものがおおく
よく池田町などを通り過ぎるたびに
高瀬川より遥か高い位置まで
田園が築かれている姿にどこから水を持ってきたのであろうと不思議でしかたがありませんでした。
ただ、農具川は名前の由来は不明なのですが
実際訪れていただければわかるのですが
農業用水路にすぎません。

その農業用水としか思えないと農具川と高瀬川の合流地点に川会神社が作られたと
川会神社に訪れて由来を知って初めて知ったのです。
しかも延喜式にものる川会神社です。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月17日
泉小太郎を調べまくる 2年目のまとめ<泉小太郎伝説の実際(74)>
1年目の結果(入明寺〜川会神社まで)
田沢神明宮に残る岩舟の伝承を紐解き
この伝承がこの地を壊滅させた武田家の次男で
海野家を継いだ「海野信親」のことの伝承ではないかと説明しました。


岩舟の先端が切り取られた後を見て
犀の角が切り取られていると思い探しました。

この石がひょっとすると墓石に使われているのではないかと
「海野信親」の墓が残る入明寺に調査に行きました。

実際に墓を見てみると
質感や大きさともに違うことがわかり
再び田沢神明宮の縁起を調べてみると
「泉小太郎は犀の広矛をつかった」という記載があり
青銅の広鉾が伝播したものではないかと推測しました。

その後、偶然に信府統記に記載のある仏崎観音寺を発見しました。


ここにも武田軍の侵略の歴史を発見し
信府統記の記述の一部は 戦国時代の御神体遷移を示したものではないかと
推測しました。
また信府統記研究者に関してはこの仏崎観音寺が有名であることを知り
信府統記の研究を始めました。
その中で「放光寺」と「川会神社」を探ることに決めました。
「放光寺」に訪ねると
「松本日光」の文字があり、泉小太郎の本名である「日光(ひかる)」から
きたものではないかと推測しました。

その後泉小太郎の祠を近くで見つけて
この地の歴史を検索しました。

すると廃仏毀釈の歴史を発見し
この地が明治時代に「戸田光則」の保身によってこの地の寺社の8割が廃寺となったという
驚愕の事実を発見します。
その中の一つ
若澤寺を訪ね「廃仏毀釈」の強烈な状況を実感します。


「放光寺」の検索を終了後
つぎの「川会神社」の検索に向かい、ここでも武田軍の進軍による壊滅の歴史を発見し
また川の氾濫で何度も神社の場所を移したことを発見しました。

またその由来より
この川会神社は
高瀬川と農具川の会う場所にできたことが判明しました。
農具川というのは農業用水として掘られた人工的な川ではないかと考え
3年目の検索に進むことになりました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
田沢神明宮に残る岩舟の伝承を紐解き
この伝承がこの地を壊滅させた武田家の次男で
海野家を継いだ「海野信親」のことの伝承ではないかと説明しました。


岩舟の先端が切り取られた後を見て
犀の角が切り取られていると思い探しました。

この石がひょっとすると墓石に使われているのではないかと
「海野信親」の墓が残る入明寺に調査に行きました。

実際に墓を見てみると
質感や大きさともに違うことがわかり
再び田沢神明宮の縁起を調べてみると
「泉小太郎は犀の広矛をつかった」という記載があり
青銅の広鉾が伝播したものではないかと推測しました。

その後、偶然に信府統記に記載のある仏崎観音寺を発見しました。


ここにも武田軍の侵略の歴史を発見し
信府統記の記述の一部は 戦国時代の御神体遷移を示したものではないかと
推測しました。
また信府統記研究者に関してはこの仏崎観音寺が有名であることを知り
信府統記の研究を始めました。
その中で「放光寺」と「川会神社」を探ることに決めました。
「放光寺」に訪ねると
「松本日光」の文字があり、泉小太郎の本名である「日光(ひかる)」から
きたものではないかと推測しました。

その後泉小太郎の祠を近くで見つけて
この地の歴史を検索しました。

すると廃仏毀釈の歴史を発見し
この地が明治時代に「戸田光則」の保身によってこの地の寺社の8割が廃寺となったという
驚愕の事実を発見します。
その中の一つ
若澤寺を訪ね「廃仏毀釈」の強烈な状況を実感します。


「放光寺」の検索を終了後
つぎの「川会神社」の検索に向かい、ここでも武田軍の進軍による壊滅の歴史を発見し
また川の氾濫で何度も神社の場所を移したことを発見しました。

またその由来より
この川会神社は
高瀬川と農具川の会う場所にできたことが判明しました。
農具川というのは農業用水として掘られた人工的な川ではないかと考え
3年目の検索に進むことになりました。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月14日
検索 川会神社2<泉小太郎伝説の実際(73)>
川会神社に行くと
そこには泉小太郎伝説の要約と
由来書がありました。


この由来書から再びこの発見物語が大きく変わり始めます。
要約のみ書きます。
景行十二年に草創とあります(田沢神明宮や信府統記とも同年)
高瀬川と木崎湖より出たる農具川の落合に鎮座。
武田信玄によって攻め込まれ、
記録および宝が灰塵と化したとあります。
その後、1780年代に氾濫にあって、現地に再建される
ここでも武田軍によって壊滅し、その後の氾濫で流されてしまっています。
建て直しの際、穂高神社の系統社として建て直されているため、その前の記録というと不明に近い状態となっているといっていいでしょう。
また、仁科濫觴記では建立に関しては、あっさりと「川の会う場所なので川会神社とした」くらいの表記しかありません。おそらく田沢神明宮と同様、川を整備するために建てられ祭祀をおこなっていた神社だと思われます。
ところで、この川会神社どことどこの川が会う場所かということですが、それは、高瀬川と農具川(のうぐがわ)です。
農具川!!次の章で詳しく説明させていただきますが、僕は以前から、この農具川こそが、仁品王、九頭子(河川大臣)、白水郎日光(あまのひかる 泉小太郎)の開発の本丸だと思っていて、池田町の用水路を調べていました。
この川の最終地点が川会神社だったのです。川会神社にきて初めて知った真実です。てっきり川会神社というのは、高瀬川と犀川がぶつかるもっと南の方にあるものと思っていたのですが、農具川といういわば用水路(私の認識は用水路でした)の合流地点に建てられていたのです。ここへきて、私はこの川会神社は、用水路完成記念に、建てられた神社だと確信しました。
3年目の検索は農具川からはじまります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
そこには泉小太郎伝説の要約と
由来書がありました。


この由来書から再びこの発見物語が大きく変わり始めます。
要約のみ書きます。
景行十二年に草創とあります(田沢神明宮や信府統記とも同年)
高瀬川と木崎湖より出たる農具川の落合に鎮座。
武田信玄によって攻め込まれ、
記録および宝が灰塵と化したとあります。
その後、1780年代に氾濫にあって、現地に再建される
ここでも武田軍によって壊滅し、その後の氾濫で流されてしまっています。
建て直しの際、穂高神社の系統社として建て直されているため、その前の記録というと不明に近い状態となっているといっていいでしょう。
また、仁科濫觴記では建立に関しては、あっさりと「川の会う場所なので川会神社とした」くらいの表記しかありません。おそらく田沢神明宮と同様、川を整備するために建てられ祭祀をおこなっていた神社だと思われます。
ところで、この川会神社どことどこの川が会う場所かということですが、それは、高瀬川と農具川(のうぐがわ)です。
農具川!!次の章で詳しく説明させていただきますが、僕は以前から、この農具川こそが、仁品王、九頭子(河川大臣)、白水郎日光(あまのひかる 泉小太郎)の開発の本丸だと思っていて、池田町の用水路を調べていました。
この川の最終地点が川会神社だったのです。川会神社にきて初めて知った真実です。てっきり川会神社というのは、高瀬川と犀川がぶつかるもっと南の方にあるものと思っていたのですが、農具川といういわば用水路(私の認識は用水路でした)の合流地点に建てられていたのです。ここへきて、私はこの川会神社は、用水路完成記念に、建てられた神社だと確信しました。
3年目の検索は農具川からはじまります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月13日
検索 川会神社1<泉小太郎伝説の実際(72)>
放光寺を訪れたことから廃仏毀釈という出来事を知り泉小太郎の信仰が明治初頭に壊滅的なダメージを負ったことを知りました。
話はだいぶ脱線しましたが信府統記に出てきた神社の検索を再開するべく
かねてより、「安曇の古代」にも「信府統記」にも触れられている川会神社に赴くことにしました。
この川会神社のある地区は池田町という地域で、あの仁科宗一郎氏がその生涯を過ごした場所となります。
信府統記では犀竜と白竜王が最後にここで出会い、泉小太郎がここに最後にたどり着き、子孫繁栄となったその場所です。
たしかに川会神社は、穂高神社とならび平安時代に書かれた延喜式という神社の総覧にも乗る由緒正しい神社で、この地方では古くから名の残る神社です。ちなみに延喜式神名帳に記載があるのは当時朝廷から重要視された神社であり、一般に式内社と言って別格の神社とされています。
実際行ってみました。
川会神社マップ

泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
話はだいぶ脱線しましたが信府統記に出てきた神社の検索を再開するべく
かねてより、「安曇の古代」にも「信府統記」にも触れられている川会神社に赴くことにしました。
この川会神社のある地区は池田町という地域で、あの仁科宗一郎氏がその生涯を過ごした場所となります。
信府統記では犀竜と白竜王が最後にここで出会い、泉小太郎がここに最後にたどり着き、子孫繁栄となったその場所です。
たしかに川会神社は、穂高神社とならび平安時代に書かれた延喜式という神社の総覧にも乗る由緒正しい神社で、この地方では古くから名の残る神社です。ちなみに延喜式神名帳に記載があるのは当時朝廷から重要視された神社であり、一般に式内社と言って別格の神社とされています。
実際行ってみました。
川会神社マップ

泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月12日
検索 二つの「信濃日光」若澤寺(廃寺)<泉小太郎伝説の実際(71)>
さっそくグーグルマップを頼りに探索をはじめました。麓にある波多神社の駐車場に車を止め、息子と二人で自転車にのり山道を進みました。
脇には若澤寺という名の通り澤がながれます。通行する人はないものの地元の方が整備をしているため、要所要所に「あと2km」等の標識があります。
自転車を押しながら何度も後悔をしながら30分ほど登りました。
もう帰ろうかと思った矢先、ようやく到着の看板が。きちんと「信濃日光」とあります。
放光寺は確実に泉小太郎との関連地で「日光」となっていますが、この地はたまたま栄えた称号としての「日光」かもしれません。
若澤寺マップ

ここからもうひと息登ると驚くべき風景が飛び込んできます。

ボキャブラリーがなくて申し訳ありませんが、まるでラピュタのような風景が山の中に唐突に現れます。廃墟と化し一度自然に飲み込まれたあとではありますが、地形にその荘厳さが残されています。
近い過去にここに栄えた伽藍があったことが偲ばれます。
入り口に当時の絵図がありましたので、みてくださいこの山奥とは思えないほどの立派な寺院があったのです。

この絵図の通りの地形がなまなましく残っており、当時の風景を体感すらできます。

木が切られて整備されていますが、おそらく近年になって保存事業により木を伐採したと思われます。
結局ここでは、「信濃日光」という文字以外、「日光泉小太郎」あるいは「あまのひかる」との関連性を見つけることはできませんでしたが、これだけの大伽藍を、保身のためという何の信条にも結びつかない行いによって、明治初頭に破壊されてしまったのです。
おそらく当時の巡礼者は、この若澤寺に詣でたあとに、放光寺に向かったと想像しています。
ちなみに麓におりてくると「盛泉寺」を発見しました。あとでネットで調べてみると、この盛泉寺には、若澤寺の寺宝の一部が避難して伝わっているそうです。

ここも「泉」とありますから、ひょっとしたら関連地かもしれません。
廃仏毀釈の言い伝えどおり、ここにも「明智学校跡」の碑があり、戸田の狂乱のあと、寺の跡地が明治時代に学校になった名残だとわかります。
ただ、そう考えると古い風習をぶち壊してでも、新しい時代を迎えなければいけなかったとも考えられます。古い風習のガレキの上に近代化があったとすると、日本の歴史の中では必要悪であったとしたがるかもしれません。
しかし、松本が全国の中でも特異的な例だと客観的に知るにあたって、つくづく戸田光則のした行為は咎められてしかるべきだと、僕は断罪します。
この行為がなければこの泉小太郎はほかの民話がそうであったように、ひょっとすると戦後の物語の絵本化などのなかで、桃太郎や、浦島太郎、金太郎くらいの知名度にはなっていたかもしれず、auのCMに出られるくらいの知名度にはなっていて、観光資源にはなるくらいの存在であったのではないかと思うのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
脇には若澤寺という名の通り澤がながれます。通行する人はないものの地元の方が整備をしているため、要所要所に「あと2km」等の標識があります。
自転車を押しながら何度も後悔をしながら30分ほど登りました。
もう帰ろうかと思った矢先、ようやく到着の看板が。きちんと「信濃日光」とあります。
放光寺は確実に泉小太郎との関連地で「日光」となっていますが、この地はたまたま栄えた称号としての「日光」かもしれません。
若澤寺マップ

ここからもうひと息登ると驚くべき風景が飛び込んできます。

ボキャブラリーがなくて申し訳ありませんが、まるでラピュタのような風景が山の中に唐突に現れます。廃墟と化し一度自然に飲み込まれたあとではありますが、地形にその荘厳さが残されています。
近い過去にここに栄えた伽藍があったことが偲ばれます。
入り口に当時の絵図がありましたので、みてくださいこの山奥とは思えないほどの立派な寺院があったのです。

この絵図の通りの地形がなまなましく残っており、当時の風景を体感すらできます。

木が切られて整備されていますが、おそらく近年になって保存事業により木を伐採したと思われます。
結局ここでは、「信濃日光」という文字以外、「日光泉小太郎」あるいは「あまのひかる」との関連性を見つけることはできませんでしたが、これだけの大伽藍を、保身のためという何の信条にも結びつかない行いによって、明治初頭に破壊されてしまったのです。
おそらく当時の巡礼者は、この若澤寺に詣でたあとに、放光寺に向かったと想像しています。
ちなみに麓におりてくると「盛泉寺」を発見しました。あとでネットで調べてみると、この盛泉寺には、若澤寺の寺宝の一部が避難して伝わっているそうです。

ここも「泉」とありますから、ひょっとしたら関連地かもしれません。
廃仏毀釈の言い伝えどおり、ここにも「明智学校跡」の碑があり、戸田の狂乱のあと、寺の跡地が明治時代に学校になった名残だとわかります。
ただ、そう考えると古い風習をぶち壊してでも、新しい時代を迎えなければいけなかったとも考えられます。古い風習のガレキの上に近代化があったとすると、日本の歴史の中では必要悪であったとしたがるかもしれません。
しかし、松本が全国の中でも特異的な例だと客観的に知るにあたって、つくづく戸田光則のした行為は咎められてしかるべきだと、僕は断罪します。
この行為がなければこの泉小太郎はほかの民話がそうであったように、ひょっとすると戦後の物語の絵本化などのなかで、桃太郎や、浦島太郎、金太郎くらいの知名度にはなっていたかもしれず、auのCMに出られるくらいの知名度にはなっていて、観光資源にはなるくらいの存在であったのではないかと思うのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月11日
検索 二つの「信濃日光」放光寺<泉小太郎伝説の実際(70)>
以前訪れた放光寺のたどった運命も「廃仏毀釈物語」の中にあります。
「信濃開拓の祖先として長野県中にその伝説を残し特に安筑平野を開発したと伝えられる日光泉小太郎の出生地が放光寺であると伝説されており、要するに当地方きっての霊場古刹を物語り、衆庶の信仰をあつめていたのであるが明治五年(1872年)に廃仏毀釈の難に遭って廃寺となり多くの寺宝を失った。」
その時の情景もかかれており、石仏などを放光寺の崖から落とし、崖下には多くの石仏などでゴロゴロしていたというので、徹底的に崩されたことを意味しています。
余談になりますが、放光寺のすぐ麓には「猿田彦神社」があります。泉小太郎は「犀の神」であり、田沢神明宮縁起によれば、中世には「塞の神」として猿田彦の化身とされていましたから、廃仏毀釈の際、放光寺の難を逃れるために作られた(分離された)神社かもしれませんし、もっと前からあったのであれば、放光寺の寺宝のいくつかはここに避難されているかもしれません。
猿田彦神社マップ 松本市

さらには、放光寺にあった寺宝のいくつかは土手から落とされた後
近隣の村に移されたことも考えられます。
ひょっとすると近隣の村々にある石仏、道祖神などはこの放光寺の崖から捨てられたものを移設したものかもしれないとも思います。
さて、前回の探索の際、放光寺が「信濃日光」とされており、その由来は「日光泉小太郎」の名にあるのではないかと考察しました。
その検索の中で、この地にもう一つ「信濃日光」とされ、信仰を集めていた「若澤寺(じゃくたくじ)」という寺があったことを知りました。それは、放光寺と同じように「戸田光則」の狂気的な廃仏毀釈により、今では廃墟、廃寺となっています。廃仏毀釈の要因の一つとなった当時の民衆暴動の地でもある「波田」にその寺はあります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月10日
検索 廃仏毀釈4<泉小太郎伝説の実際(69)>
この廃仏毀釈により、多くの寺が取り壊され接収されました。
寺の跡地の多くは、明治政府の指導のもと「小学校」などの学校施設の敷地となり、明治中頃には全国的にもまれにみる「小学校普及率」を示しました。
みなさんご存知の「長野県は教育県」といわれる所以となりました。
こんな歴史を、この地で育った僕も知りませんでした。
一度壊され変えられた考え方は、この地域の官庁的な思考として残り、(維新とはそういうものであるということです)第二次世界大戦までの近代化とも合間って、この地域に影響を及ぼし続け、およそ50年ほどのちには、古い習俗の多くは、新しい時代の波とともに消え去ってしまったといえましょう。
その中でも、泉小太郎の伝承は、最後の松本藩主である戸田光則の保身的な圧政に対して、反旗を広げた一揆的なアイコンになってしまったのかもしれません。戸田の圧政に苦しむ民衆は、泉小太郎を胸に圧政に対して反旗を翻し、そのためそれを鎮圧するために、廃仏毀釈というかたちで、当時泉小太郎を神仏習合の形で祀っていた寺社が取り潰されたのかもしれません。
泉小太郎は、田沢神明宮の由緒では、中世には円満寺という寺として祀られていました。その後、寺という仏教施設として泉小太郎は信仰されていたとも考えられます。仏崎も観音寺というお寺に泉小太郎は祀られていましたし、そもそもその頃は、寺社と神社の区別はさほどなかったかもしれません。
「廃仏毀釈物語」を引用すれば
「当時における松本地方の(神仏)習合思想は民衆の間では疑う余地なく、日常茶飯事であり、それが当然の如く行われていたのであるし、寺社間においても当地においては、僧は神を敬い神職も仏を敬愛し、ともに尊重し合っていたのであろう。」
ところでこの廃仏毀釈で多くの寺が被害を被ったため、(その範囲が大きすぎて)実害はどれほどのものだったかは不明ですが、僕には気になる二つの寺があります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
寺の跡地の多くは、明治政府の指導のもと「小学校」などの学校施設の敷地となり、明治中頃には全国的にもまれにみる「小学校普及率」を示しました。
みなさんご存知の「長野県は教育県」といわれる所以となりました。
こんな歴史を、この地で育った僕も知りませんでした。
一度壊され変えられた考え方は、この地域の官庁的な思考として残り、(維新とはそういうものであるということです)第二次世界大戦までの近代化とも合間って、この地域に影響を及ぼし続け、およそ50年ほどのちには、古い習俗の多くは、新しい時代の波とともに消え去ってしまったといえましょう。
その中でも、泉小太郎の伝承は、最後の松本藩主である戸田光則の保身的な圧政に対して、反旗を広げた一揆的なアイコンになってしまったのかもしれません。戸田の圧政に苦しむ民衆は、泉小太郎を胸に圧政に対して反旗を翻し、そのためそれを鎮圧するために、廃仏毀釈というかたちで、当時泉小太郎を神仏習合の形で祀っていた寺社が取り潰されたのかもしれません。
泉小太郎は、田沢神明宮の由緒では、中世には円満寺という寺として祀られていました。その後、寺という仏教施設として泉小太郎は信仰されていたとも考えられます。仏崎も観音寺というお寺に泉小太郎は祀られていましたし、そもそもその頃は、寺社と神社の区別はさほどなかったかもしれません。
「廃仏毀釈物語」を引用すれば
「当時における松本地方の(神仏)習合思想は民衆の間では疑う余地なく、日常茶飯事であり、それが当然の如く行われていたのであるし、寺社間においても当地においては、僧は神を敬い神職も仏を敬愛し、ともに尊重し合っていたのであろう。」
ところでこの廃仏毀釈で多くの寺が被害を被ったため、(その範囲が大きすぎて)実害はどれほどのものだったかは不明ですが、僕には気になる二つの寺があります。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月09日
検索 廃仏毀釈3<泉小太郎伝説の実際(68)>
戸田光則の政府にあてた手紙を載せてみます。これを読んでいただければこの戸田光則のヒステリックな感情を感じていただけると思います。
「臣光則は才なく徳うすき身でありながら、松本藩知事の任を承り厚く恩沢を蒙り、日夜勉励致しましたけれども、管内は僻地であり民衆の気持ちは頑固、その上仏教がはびこり僧侶はずる賢く、ことある毎に便乗して民心を惑わして、幾多の財宝をかすめとって邪悪の仏教を盛にして、正道を害して、我が国固有の大義を妨げ、敬神の令典は急に行われ難く、まことに憂慮の至りであります。私光則をはじめ配下の士、庶民に至るまで仏教を信ずるものはおりません。祭政一致なる我が国の大典を世界に類なく普くゆきわたらせるご趣旨を体して、まず臣光則一家を神葬祭に改典し、松本藩士族、卒庶民に至るまで、改典し、管内悉く神葬祭に改めさせ度く考えております。(略)」
このおびえた感情によって、このあと自らの菩提寺を破壊し、廃仏毀釈を管内に吹き荒れさせまくります。
のちに、この状況を知った政府が返書した内容と実際の施策とがあまりに違い、当事者たちが「ア然とした」とあるように、まったくの個人的な拡大解釈、かってな忖度で松本藩の地区の寺社仏閣は壊滅してしまうのです。
何度もいいますが、ここまでやったところは松本やいくつかの例外の場所以外には例がなく、これは政府の施策でもなんでもなく、戸田光則の独断であったのです。
そして、その時に壊滅させられた民衆信仰のひとつが、泉小太郎信仰なのです。
ひょっとすると「泉小太郎伝説」の一番の壊滅要因は、武田氏でも飢饉でもなく、この戸田光則の廃仏毀釈だったかもしれないという驚愕の歴史を発見してしまったのです。
そう思うと今ものこる泉小太郎の祠も見え方が変わらないでしょうか
誰かが守り切った歴史なのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
「臣光則は才なく徳うすき身でありながら、松本藩知事の任を承り厚く恩沢を蒙り、日夜勉励致しましたけれども、管内は僻地であり民衆の気持ちは頑固、その上仏教がはびこり僧侶はずる賢く、ことある毎に便乗して民心を惑わして、幾多の財宝をかすめとって邪悪の仏教を盛にして、正道を害して、我が国固有の大義を妨げ、敬神の令典は急に行われ難く、まことに憂慮の至りであります。私光則をはじめ配下の士、庶民に至るまで仏教を信ずるものはおりません。祭政一致なる我が国の大典を世界に類なく普くゆきわたらせるご趣旨を体して、まず臣光則一家を神葬祭に改典し、松本藩士族、卒庶民に至るまで、改典し、管内悉く神葬祭に改めさせ度く考えております。(略)」
このおびえた感情によって、このあと自らの菩提寺を破壊し、廃仏毀釈を管内に吹き荒れさせまくります。
のちに、この状況を知った政府が返書した内容と実際の施策とがあまりに違い、当事者たちが「ア然とした」とあるように、まったくの個人的な拡大解釈、かってな忖度で松本藩の地区の寺社仏閣は壊滅してしまうのです。
何度もいいますが、ここまでやったところは松本やいくつかの例外の場所以外には例がなく、これは政府の施策でもなんでもなく、戸田光則の独断であったのです。
そして、その時に壊滅させられた民衆信仰のひとつが、泉小太郎信仰なのです。
ひょっとすると「泉小太郎伝説」の一番の壊滅要因は、武田氏でも飢饉でもなく、この戸田光則の廃仏毀釈だったかもしれないという驚愕の歴史を発見してしまったのです。
そう思うと今ものこる泉小太郎の祠も見え方が変わらないでしょうか
誰かが守り切った歴史なのです。

泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月08日
検索 廃仏毀釈2<泉小太郎伝説の実際(67)>
恐怖に怯えながらも、さっそく、県立図書館に向かい松本地区における廃仏毀釈について調べました。司書さんに「松本地区の廃仏毀釈について知りたいのですが?」と確認すると早速検索していただき「廃仏毀釈物語 熊谷定義 著」を示してくれました。
長野県立図書館

長野県立図書館は、長野県の資料については貸し出し不可なのですが、例えば「明治以前日本土木史」や柳田國男の「桃太郎の誕生」のような希少本でも簡単に借りられる素敵な図書館です。ここで、長野県の資料を幾度となくコピーしまくっていました。
松本藩における廃仏毀釈のことの次第は、先程引用させていただいた内容でほぼ間違いないのですが、詳細を読むとこの戸田光則に対しての不信感(怒り)を感じずにはいられません。
佐幕派(徳川幕府側)であった戸田光則は薩長の要請(当時は朝命)にも応えず、馬鹿にしていたといえます。それが薩長の勝利に終わり明治政府が樹立され、その際、叱られ謹慎させられるに至り、「戸田光則」は狼狽し右往左往します。
そこから、保身のため、明治政府に媚び、信用回復をはかるため、神仏分離を拡大解釈し、廃仏毀釈を強行的に進めます。
そこには財政的な問題もあったともいわれます。
明治政府に睨まれた松本藩は、つぎつぎと出兵を命じられます
「しかし、信用恢復の為には、過分な戦争協力や莫大な献金を強要されても従順たらざるを得ず藩財政は破綻に近づいていた。特に謹慎解除直後の三月末には関東出陣、続く衝鋒隊の飯山占領による飯山戦争への参加、四月末からの北越、東北への出兵等、多額経費は税収、献金で間にあわず藩札に続く藩札の発行であった。」(廃仏毀釈物語より)
財政難により、経済混乱と社会不安に陥ります。波田での米騒動や、会田、麻績での富豪襲撃事件などが勃発し、この動きは民衆から士分にまで波及したため、信教政策として廃仏毀釈を行い、暴動を抑えようとしたとあります。
このヒステリックとも言える廃仏毀釈は戸田光則ただ一人の保身のために行われたと言っても過言ではなく、そこには学問的思想的な純粋な発露は見当たらず、もし、なんらかの思想に基づいたものであれば、これ程悲惨で不合理な方法をとらなかったであろうと、「廃仏毀釈物語」の熊谷氏も述べています。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
長野県立図書館

長野県立図書館は、長野県の資料については貸し出し不可なのですが、例えば「明治以前日本土木史」や柳田國男の「桃太郎の誕生」のような希少本でも簡単に借りられる素敵な図書館です。ここで、長野県の資料を幾度となくコピーしまくっていました。
松本藩における廃仏毀釈のことの次第は、先程引用させていただいた内容でほぼ間違いないのですが、詳細を読むとこの戸田光則に対しての不信感(怒り)を感じずにはいられません。
佐幕派(徳川幕府側)であった戸田光則は薩長の要請(当時は朝命)にも応えず、馬鹿にしていたといえます。それが薩長の勝利に終わり明治政府が樹立され、その際、叱られ謹慎させられるに至り、「戸田光則」は狼狽し右往左往します。
そこから、保身のため、明治政府に媚び、信用回復をはかるため、神仏分離を拡大解釈し、廃仏毀釈を強行的に進めます。
そこには財政的な問題もあったともいわれます。
明治政府に睨まれた松本藩は、つぎつぎと出兵を命じられます
「しかし、信用恢復の為には、過分な戦争協力や莫大な献金を強要されても従順たらざるを得ず藩財政は破綻に近づいていた。特に謹慎解除直後の三月末には関東出陣、続く衝鋒隊の飯山占領による飯山戦争への参加、四月末からの北越、東北への出兵等、多額経費は税収、献金で間にあわず藩札に続く藩札の発行であった。」(廃仏毀釈物語より)
財政難により、経済混乱と社会不安に陥ります。波田での米騒動や、会田、麻績での富豪襲撃事件などが勃発し、この動きは民衆から士分にまで波及したため、信教政策として廃仏毀釈を行い、暴動を抑えようとしたとあります。
このヒステリックとも言える廃仏毀釈は戸田光則ただ一人の保身のために行われたと言っても過言ではなく、そこには学問的思想的な純粋な発露は見当たらず、もし、なんらかの思想に基づいたものであれば、これ程悲惨で不合理な方法をとらなかったであろうと、「廃仏毀釈物語」の熊谷氏も述べています。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら