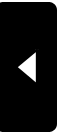2022年04月07日
検索 廃仏毀釈1<泉小太郎伝説の実際(66)>
廃仏毀釈との出会いはまったくの偶然でした。
泉小太郎の祠を発見してからしばらくたったあと
兄の本棚にあった本を見るともなしにみていました。
その中の一冊の 内田樹 著 「日本習合論」を読んでいた時
何気なく書かれた一文に衝撃を受けます。
廃仏毀釈について論じるその論稿の中で、このような一文があるのです。
「廃仏毀釈運動が熾烈だったのは鹿児島、宮崎、土佐、隠岐、松本です。」(日本習合論)
「えっ なんでここに松本?」皆さんも違和感を受けませんか?
廃仏毀釈は歴史の授業の際にほんの少しだけ触れたことがある言葉でした。
僕はこの廃仏毀釈は
明治政府の政策で、神社への信仰に一本化し天皇崇拝を推し進めるため
全国で施行されたものと勝手に解釈していましたが
この一文を見る限り
とても全国とは言えないものだと直感します。
それほどこの「松本」という地名に違和感を感じます。
まずは廃仏毀釈について調べてみましょう。
廃仏毀釈とは ウィキペディアより
明治期の神仏分離と廃仏毀釈
大政奉還後に成立した新政府によって慶応4年3月13日(1868年4月5日)に発せられた
太政官布告(通称「神仏分離令」「神仏判然令」)
および明治3年1月3日(1870年2月3日)に出された詔書「大教宣布」などの
政策を拡大解釈し暴走した民衆をきっかけに引き起こされた
仏教施設の破壊などを指す。
つまり僕が勝手に明治政府の政策だと思っていたものは
公的な政策などではなく政府の意図を拡大解釈した民衆運動だったというのです。
そして調べてみてわかったのは
松本における廃仏毀釈は
そんな民衆運動でも、何かの理念による崇高運動でもなく
保身によってなされた忖度(そんたく)に過ぎなかったことが判明するのです。
先程の「日本習合論」の続きを引用します。
(中略)水戸藩や津和野藩は国学がさかんで
幕末から廃仏運動のフロントランナーでしたから
廃仏運動がエスカレートした理由はわかります。
けれども、その他の地域ではどうして廃仏運動が行われたのか、
必ずしも理由が定かではありません。
たとえば、松本藩知事の戸田光則はファナティックな廃仏運動を推進しました。
それは松本藩が戊辰戦争のときに幕府につくか薩長につくか
はっきりした態度をとらずにいたので
明治政府に忠誠を誇示する必要があったからだとされています。
戸田はもともと松平姓で徳川家の親戚でした。
ですから、神仏分離令を「拡大解釈」することで、新政府に恭順の姿勢をアピールすることには必然性があったのです。
戸田の廃仏運動は寺院整理にとどまらず、盆行事の廃止、位牌や仏壇の撤去まで行って、ついに領内の八割の寺院を廃寺としました。( 日本習合論より)
という驚愕な事実が浮かび上がるのです。
この地区で生まれ育ったのにまったく知らなかった事実でした。
しかもてっきり全国的に行われたことかと思っていたら
松本が特異的に激しく行われたのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
泉小太郎の祠を発見してからしばらくたったあと
兄の本棚にあった本を見るともなしにみていました。
その中の一冊の 内田樹 著 「日本習合論」を読んでいた時
何気なく書かれた一文に衝撃を受けます。
廃仏毀釈について論じるその論稿の中で、このような一文があるのです。
「廃仏毀釈運動が熾烈だったのは鹿児島、宮崎、土佐、隠岐、松本です。」(日本習合論)
「えっ なんでここに松本?」皆さんも違和感を受けませんか?
廃仏毀釈は歴史の授業の際にほんの少しだけ触れたことがある言葉でした。
僕はこの廃仏毀釈は
明治政府の政策で、神社への信仰に一本化し天皇崇拝を推し進めるため
全国で施行されたものと勝手に解釈していましたが
この一文を見る限り
とても全国とは言えないものだと直感します。
それほどこの「松本」という地名に違和感を感じます。
まずは廃仏毀釈について調べてみましょう。
廃仏毀釈とは ウィキペディアより
明治期の神仏分離と廃仏毀釈
大政奉還後に成立した新政府によって慶応4年3月13日(1868年4月5日)に発せられた
太政官布告(通称「神仏分離令」「神仏判然令」)
および明治3年1月3日(1870年2月3日)に出された詔書「大教宣布」などの
政策を拡大解釈し暴走した民衆をきっかけに引き起こされた
仏教施設の破壊などを指す。
つまり僕が勝手に明治政府の政策だと思っていたものは
公的な政策などではなく政府の意図を拡大解釈した民衆運動だったというのです。
そして調べてみてわかったのは
松本における廃仏毀釈は
そんな民衆運動でも、何かの理念による崇高運動でもなく
保身によってなされた忖度(そんたく)に過ぎなかったことが判明するのです。
先程の「日本習合論」の続きを引用します。
(中略)水戸藩や津和野藩は国学がさかんで
幕末から廃仏運動のフロントランナーでしたから
廃仏運動がエスカレートした理由はわかります。
けれども、その他の地域ではどうして廃仏運動が行われたのか、
必ずしも理由が定かではありません。
たとえば、松本藩知事の戸田光則はファナティックな廃仏運動を推進しました。
それは松本藩が戊辰戦争のときに幕府につくか薩長につくか
はっきりした態度をとらずにいたので
明治政府に忠誠を誇示する必要があったからだとされています。
戸田はもともと松平姓で徳川家の親戚でした。
ですから、神仏分離令を「拡大解釈」することで、新政府に恭順の姿勢をアピールすることには必然性があったのです。
戸田の廃仏運動は寺院整理にとどまらず、盆行事の廃止、位牌や仏壇の撤去まで行って、ついに領内の八割の寺院を廃寺としました。( 日本習合論より)
という驚愕な事実が浮かび上がるのです。
この地区で生まれ育ったのにまったく知らなかった事実でした。
しかもてっきり全国的に行われたことかと思っていたら
松本が特異的に激しく行われたのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月06日
検索 放光寺4<泉小太郎伝説の実際(65)>
放光寺を一通りまわり
近くの城山公園の駐車場に帰ろうとしたとき
道の途中に「泉小太郎」の祠を発見しました。
泉小太郎のほこら

こんなひっそりとした状況ですが、それでもこのような形で信仰が残っていることに
敬意を払いたいとおもます。
僕は賽銭でもと思い失礼ながら祠の窓をあけ持っていた千円札を奉納しました。
しかし、この後、このひっそりとした状況となった驚愕の真実が
判明することになります。
その驚愕の真実はこの後 述べていくとして
泉小太郎を探究したのちに判明しているところでいえば
この小さな祠こそが今現存する
唯一の泉小太郎の信仰物 です。
泉小太郎関連地は多くありますし、
仏崎 穂高神社など泉小太郎像はありますが
信仰形態をとっていません。
また、田沢神明宮も泉小太郎創建となっていますが
祀られてはいません。
この小さな祠ですが
実はこのような小さな祠こそが
この地の民が守り抜いた歴史そのものであるのです。
この地に武田軍が攻めてきて
この地域を壊滅させたと説明してきました。
しかし それに匹敵するほどの破壊が
明治初期にこの地に吹き荒れたのです。
その破壊の名は「廃仏毀釈」
知ってそうで知らないこの地の歴史をこの後深掘りしていきます。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
近くの城山公園の駐車場に帰ろうとしたとき
道の途中に「泉小太郎」の祠を発見しました。
泉小太郎のほこら

こんなひっそりとした状況ですが、それでもこのような形で信仰が残っていることに
敬意を払いたいとおもます。
僕は賽銭でもと思い失礼ながら祠の窓をあけ持っていた千円札を奉納しました。
しかし、この後、このひっそりとした状況となった驚愕の真実が
判明することになります。
その驚愕の真実はこの後 述べていくとして
泉小太郎を探究したのちに判明しているところでいえば
この小さな祠こそが今現存する
唯一の泉小太郎の信仰物 です。
泉小太郎関連地は多くありますし、
仏崎 穂高神社など泉小太郎像はありますが
信仰形態をとっていません。
また、田沢神明宮も泉小太郎創建となっていますが
祀られてはいません。
この小さな祠ですが
実はこのような小さな祠こそが
この地の民が守り抜いた歴史そのものであるのです。
この地に武田軍が攻めてきて
この地域を壊滅させたと説明してきました。
しかし それに匹敵するほどの破壊が
明治初期にこの地に吹き荒れたのです。
その破壊の名は「廃仏毀釈」
知ってそうで知らないこの地の歴史をこの後深掘りしていきます。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月05日
検索 放光寺3<泉小太郎伝説の実際(64)>
放光寺は
松本の城山公園の裏手にあるお寺のため
城山公園の駐車場に車を停めて向かいました。
もともとこの山自体が放光寺山であり
武田軍がくるまではここにも城が築かれていました
おそらく昔は寺の規模もこの山全体に広がっていたのではないかと推定します。
放光寺マップ

期待とは違い
境内にはなにも泉小太郎らしいものはありませんでした。
ただ
駐車場や看板などには
「松本日光」の文字があります。
仁科濫觴記によれば泉小太郎の本名は「日光(ひかる)」ですので
おそらく、初めは「光城山」と同じように「日光(ひかる」の名から来たと
推定します。
「日光(ひかる)」の文字が江戸時代に
徳川家康の日光東照宮ために一人歩きしてしまい
「日光(にっこう)」となってしまい
「松本日光」になったと推察されます。
もともとは「日光(ひかる)」を祀る場所だったと思われます。
「日光」が「ひかる」であり、日光泉小太郎の名を知っている人間から
すると至極当たり前の推論ですが
日光という名前が邪魔になり
江戸時代に日光東照宮と関係づけられてしまったため埋もれてしまったとしか思えません。
放光寺は信府統記にも「泉小太郎」が育った場所でありますし
光城山からは山続きの終点の場所でもありますから
ここにも「ひかる信仰」があったことは間違いないかと思います。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
松本の城山公園の裏手にあるお寺のため
城山公園の駐車場に車を停めて向かいました。
もともとこの山自体が放光寺山であり
武田軍がくるまではここにも城が築かれていました
おそらく昔は寺の規模もこの山全体に広がっていたのではないかと推定します。
放光寺マップ

期待とは違い
境内にはなにも泉小太郎らしいものはありませんでした。
ただ
駐車場や看板などには
「松本日光」の文字があります。
仁科濫觴記によれば泉小太郎の本名は「日光(ひかる)」ですので
おそらく、初めは「光城山」と同じように「日光(ひかる」の名から来たと
推定します。
「日光(ひかる)」の文字が江戸時代に
徳川家康の日光東照宮ために一人歩きしてしまい
「日光(にっこう)」となってしまい
「松本日光」になったと推察されます。
もともとは「日光(ひかる)」を祀る場所だったと思われます。
「日光」が「ひかる」であり、日光泉小太郎の名を知っている人間から
すると至極当たり前の推論ですが
日光という名前が邪魔になり
江戸時代に日光東照宮と関係づけられてしまったため埋もれてしまったとしか思えません。
放光寺は信府統記にも「泉小太郎」が育った場所でありますし
光城山からは山続きの終点の場所でもありますから
ここにも「ひかる信仰」があったことは間違いないかと思います。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月04日
検索 放光寺2<泉小太郎伝説の実際(63)>
前回、この放光寺の丘で「安曇平の雲海」をみて
「この地域は本当は、昔 みずうみだったのでは」という仮説をたてていたと述べました。。
この経験があったため
「泉小太郎伝説」にある「この地域が湖だった」という物語は
ごく早い時期に「空想である」と実感できましたし
「その地域の特殊な自然環境が伝承をつくりだす」ということも
体感として理解することができました。
その高校時代を過ごした場所が
まさに放光寺の元敷地と想定されるのです。
(グーグルマップではうっすらと「放光寺」と記載)
信府統記では「泉小太郎が育った場所」とされる放光寺です。
しかし実は
この「放光寺」こそが
信府統記を信ずるに値しないと
一蹴してしまうことになった原因の場所だったのです。
それは、信府統記の中にある次の一文です
「景行天皇十二年、放光寺で育った泉小太郎は〜」
この表現は明らかに、でたらめだとすぐわかりますよね。
なぜなら景行天皇といえば、古墳時代早期もしくは弥生時代晩期ですから
放光寺という仏教施設は存在しているわけがありません。(笑)
(日本への仏教伝来はこの2〜3世紀後くらい)
この一文が冒頭にあったために、僕は信府統記をでたらめの伝承としていました。
これすらも運命的な何かを感じます。
学生時代、この地が湖だったと空想し、
この探究のきっかけとなった場所がまさに放光寺で
泉小太郎を知り信府統記(しんぷとうき)は
でたらめだと一蹴したきっかけが、この放光寺で
遠回りをして 仁科濫觴記(にしならんしょうき)を知り
各地を廻り、仏崎を見つけ、もう一度振り出しに戻ってきての
放光寺なのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
「この地域は本当は、昔 みずうみだったのでは」という仮説をたてていたと述べました。。
この経験があったため
「泉小太郎伝説」にある「この地域が湖だった」という物語は
ごく早い時期に「空想である」と実感できましたし
「その地域の特殊な自然環境が伝承をつくりだす」ということも
体感として理解することができました。
その高校時代を過ごした場所が
まさに放光寺の元敷地と想定されるのです。
(グーグルマップではうっすらと「放光寺」と記載)
信府統記では「泉小太郎が育った場所」とされる放光寺です。
しかし実は
この「放光寺」こそが
信府統記を信ずるに値しないと
一蹴してしまうことになった原因の場所だったのです。
それは、信府統記の中にある次の一文です
「景行天皇十二年、放光寺で育った泉小太郎は〜」
この表現は明らかに、でたらめだとすぐわかりますよね。
なぜなら景行天皇といえば、古墳時代早期もしくは弥生時代晩期ですから
放光寺という仏教施設は存在しているわけがありません。(笑)
(日本への仏教伝来はこの2〜3世紀後くらい)
この一文が冒頭にあったために、僕は信府統記をでたらめの伝承としていました。
これすらも運命的な何かを感じます。
学生時代、この地が湖だったと空想し、
この探究のきっかけとなった場所がまさに放光寺で
泉小太郎を知り信府統記(しんぷとうき)は
でたらめだと一蹴したきっかけが、この放光寺で
遠回りをして 仁科濫觴記(にしならんしょうき)を知り
各地を廻り、仏崎を見つけ、もう一度振り出しに戻ってきての
放光寺なのです。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月03日
検索 放光寺1<泉小太郎伝説の実際(62)>
放光寺の所在地をずっと知らずに過ごしていましたが
その場所を検索したときに驚きました。
高校時代、悩んでいたときお気に入りの場所がありました。
城山公園からアルプス公園にぬける遊歩道で
西を眺めると壮大な穂高連峰がそびえ
間にある安曇野がはるか眼下に広がり
車がミニカーに見えるほどの絶景です。
写真ではわかりにくいのですが絶景です。

そこにあるベンチが当時の僕の隠れ家でした。
ほぼ1日いても3人くらいしか通らない場所で
授業を休んだ高校生がいるにはもってこいの場所でした。

この隠れ家で時間を過ごしているとき
眼下に流れる川をみて、この360度ぐるっと山に囲まれた地形から
この盆地に降った雨が、どうやって日本海に注ぐのだろうと不思議でしかたがありませんでした。
またある時、早朝に行くと(学校にはいかずに)
この安曇野一帯に、雲海(霧?かすみ?)がたまり
はるか向こうの穂高連峰と自分のたっている場所との間に巨大な湖のような情景が出現したのでした。
当時は、泉小太郎の伝説も、たつのこたろうも知りませんでしたが
「この地域は本当は、昔 みずうみだったのでは」という仮説を
僕もたてていたのでした。
ですから、泉小太郎伝説に出会った時は衝撃的で
こうして気の済むまで探すまでになってしまったのかもしれません。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
その場所を検索したときに驚きました。
高校時代、悩んでいたときお気に入りの場所がありました。
城山公園からアルプス公園にぬける遊歩道で
西を眺めると壮大な穂高連峰がそびえ
間にある安曇野がはるか眼下に広がり
車がミニカーに見えるほどの絶景です。
写真ではわかりにくいのですが絶景です。

そこにあるベンチが当時の僕の隠れ家でした。
ほぼ1日いても3人くらいしか通らない場所で
授業を休んだ高校生がいるにはもってこいの場所でした。

この隠れ家で時間を過ごしているとき
眼下に流れる川をみて、この360度ぐるっと山に囲まれた地形から
この盆地に降った雨が、どうやって日本海に注ぐのだろうと不思議でしかたがありませんでした。
またある時、早朝に行くと(学校にはいかずに)
この安曇野一帯に、雲海(霧?かすみ?)がたまり
はるか向こうの穂高連峰と自分のたっている場所との間に巨大な湖のような情景が出現したのでした。
当時は、泉小太郎の伝説も、たつのこたろうも知りませんでしたが
「この地域は本当は、昔 みずうみだったのでは」という仮説を
僕もたてていたのでした。
ですから、泉小太郎伝説に出会った時は衝撃的で
こうして気の済むまで探すまでになってしまったのかもしれません。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月02日
コラム1 泉小太郎とお船祭り<泉小太郎伝説の実際(61)>
少しここら辺で、目先を変えてコラムです。
泉小太郎とお船祭りです。
仕事で安曇野市役所に行くことがあり、出入り業者との待ち合わせの際、その担当者が時間を間違え1時間待ちぼうけとなりました。
それならばと、すぐ近くにある安曇野市豊科郷土博物館に寄らせていただきました。
特に何を探すわけでもなかったのですが、お舟祭りの特集をしていましたので見ることにしました。
この日感じたことをコラムとして書きます。(話は少し脱線です)
安曇野市豊科郷土博物館

お舟祭りは穂高神社の例祭で有名で、海のない長野県における船の祭りとして安曇族の伝承としても古代のロマンあふれるものです。
穂高神社の祭りとしては「白村江の戦い」に登場する安曇氏である「安曇比羅夫」を関連づけて説明されることが多い気がします。

安曇野市観光協会より
しかし僕は当初、お舟祭りこそが泉小太郎が堤を開いたときにつかった古代器具を伝承したもので、船と船がぶつかるシーンが、開墾シーンを再現したものではないかと想像したものでした。
下の絵の右図のようなないようで
泉小太郎が竜にのって湖をきりひらくときに
石をぶつけた様が祭りとなって残ったのかもと考えました。

しかし、その日、展示をみて考えが一新されました。
お舟祭りは、安曇野各地にあり
特に岩舟が残る田沢神明宮のある安曇野東地区にも広がる一帯にもあることがわかりました。

わかりにくいですが、丸のついた部分がお舟まつりの分布です。分布地域が川沿いあり、川に関連した祭りだと考えられます。

さらには穂高神社のお舟祭りがとりわけ大きく船型となっていますが、その他はたいてい、小さな山車くらいの船を曳き歩くという祭りなのです。
分布地区に広がるさまざまな「船」をみると
穂高神社の船は後々巨大化したもので
もともとは山車を引くぐらいの規模の祭りだったことが
推察されます。
この近くには川沿いの各地で「船」と呼ばれる山車を引く祭りが広い範囲で分布している
これに気がついた時に
田沢神明宮の岩舟の考察が頭をよぎるのです。


山梨の信玄堤おみゆきさんのところでも述べましたが
ひょっとするとこの「岩舟」は河川メンテナンスに使われていた
ロードローラーのような役目をしていたかもしれないと述べました。
また田沢神明宮には河川メンテナンスにおいて1年に一度
河川沿いを点検した祭りがあったことを示す縁起があります。
河川の堤防は年に一度ほど押し固める必要があったという
ことは信玄堤 おみゆきさんの時も述べましたが
そのような祭りの残りが
お船祭りなのではないかと考えたのです。
安曇族の安曇比羅夫は後世の勝手な付け加えであるというのは専門家も指摘する常識的な判断で
田沢神明宮(もしくはこの地区の河川付近)の岩船曳きがもともとあって
それが穂高神社では年々拡大されていき今のようなお舟まつりになったと考えるほうが妥当ではないかと
コラムを残したいと思います。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
泉小太郎とお船祭りです。
仕事で安曇野市役所に行くことがあり、出入り業者との待ち合わせの際、その担当者が時間を間違え1時間待ちぼうけとなりました。
それならばと、すぐ近くにある安曇野市豊科郷土博物館に寄らせていただきました。
特に何を探すわけでもなかったのですが、お舟祭りの特集をしていましたので見ることにしました。
この日感じたことをコラムとして書きます。(話は少し脱線です)
安曇野市豊科郷土博物館

お舟祭りは穂高神社の例祭で有名で、海のない長野県における船の祭りとして安曇族の伝承としても古代のロマンあふれるものです。
穂高神社の祭りとしては「白村江の戦い」に登場する安曇氏である「安曇比羅夫」を関連づけて説明されることが多い気がします。

安曇野市観光協会より
しかし僕は当初、お舟祭りこそが泉小太郎が堤を開いたときにつかった古代器具を伝承したもので、船と船がぶつかるシーンが、開墾シーンを再現したものではないかと想像したものでした。
下の絵の右図のようなないようで
泉小太郎が竜にのって湖をきりひらくときに
石をぶつけた様が祭りとなって残ったのかもと考えました。

しかし、その日、展示をみて考えが一新されました。
お舟祭りは、安曇野各地にあり
特に岩舟が残る田沢神明宮のある安曇野東地区にも広がる一帯にもあることがわかりました。

わかりにくいですが、丸のついた部分がお舟まつりの分布です。分布地域が川沿いあり、川に関連した祭りだと考えられます。

さらには穂高神社のお舟祭りがとりわけ大きく船型となっていますが、その他はたいてい、小さな山車くらいの船を曳き歩くという祭りなのです。
分布地区に広がるさまざまな「船」をみると
穂高神社の船は後々巨大化したもので
もともとは山車を引くぐらいの規模の祭りだったことが
推察されます。
この近くには川沿いの各地で「船」と呼ばれる山車を引く祭りが広い範囲で分布している
これに気がついた時に
田沢神明宮の岩舟の考察が頭をよぎるのです。


山梨の信玄堤おみゆきさんのところでも述べましたが
ひょっとするとこの「岩舟」は河川メンテナンスに使われていた
ロードローラーのような役目をしていたかもしれないと述べました。
また田沢神明宮には河川メンテナンスにおいて1年に一度
河川沿いを点検した祭りがあったことを示す縁起があります。
河川の堤防は年に一度ほど押し固める必要があったという
ことは信玄堤 おみゆきさんの時も述べましたが
そのような祭りの残りが
お船祭りなのではないかと考えたのです。
安曇族の安曇比羅夫は後世の勝手な付け加えであるというのは専門家も指摘する常識的な判断で
田沢神明宮(もしくはこの地区の河川付近)の岩船曳きがもともとあって
それが穂高神社では年々拡大されていき今のようなお舟まつりになったと考えるほうが妥当ではないかと
コラムを残したいと思います。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
2022年04月01日
検索 信府統記6<泉小太郎伝説の実際(60)>
信府統記で手がかりになるであろう地名がいくつかありました。
白竜王に関係するところは
東北信の地区にあたるもののため
後日に回すとして
「仏崎」
「放光寺」(ほうこうじ)
「鉢伏山」(はちぶせやま)
「川会」(かわい)
「仏崎」の発見により
「仏崎」については
私は犀竜の御神体である犀の角である「犀の広鉾(ひろほこ)(青銅器を推定)」が
武田軍の戦火を逃れ、仏崎に移転させたという可能性を考えました。
その御神体の遷移が信府統記②の段落に記された伝承にかわったものではないかという
考察をしました。
それではそれ以外の地区はどうでしょうか。
「鉢伏山」については後日報告いたします。
おそらく山岳信仰と融合して泉小太郎もしくは
あまのひかる(白水郎日光)、日光泉小太郎の名と
大日如来あたりが習合されたのではないかと思っています。
大日如来との習合化は
上田地区方面で顕著に現れる状況だと思いますが
こちらもまだ未調査です。
現状調査済みは
のこり2箇所
「放光寺」
「川会」
ふたつともはっきりとその場所があります。
次回から「放光寺」について調べていきましょう。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら
白竜王に関係するところは
東北信の地区にあたるもののため
後日に回すとして
「仏崎」
「放光寺」(ほうこうじ)
「鉢伏山」(はちぶせやま)
「川会」(かわい)
「仏崎」の発見により
「仏崎」については
私は犀竜の御神体である犀の角である「犀の広鉾(ひろほこ)(青銅器を推定)」が
武田軍の戦火を逃れ、仏崎に移転させたという可能性を考えました。
その御神体の遷移が信府統記②の段落に記された伝承にかわったものではないかという
考察をしました。
それではそれ以外の地区はどうでしょうか。
「鉢伏山」については後日報告いたします。
おそらく山岳信仰と融合して泉小太郎もしくは
あまのひかる(白水郎日光)、日光泉小太郎の名と
大日如来あたりが習合されたのではないかと思っています。
大日如来との習合化は
上田地区方面で顕著に現れる状況だと思いますが
こちらもまだ未調査です。
現状調査済みは
のこり2箇所
「放光寺」
「川会」
ふたつともはっきりとその場所があります。
次回から「放光寺」について調べていきましょう。
泉小太郎伝説の実際を最初から読む
泉小太郎伝説を調べまくるの 目次はこちら